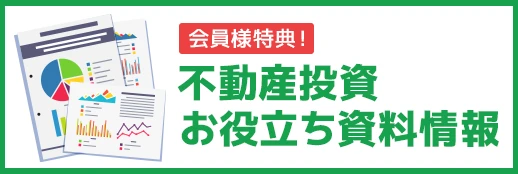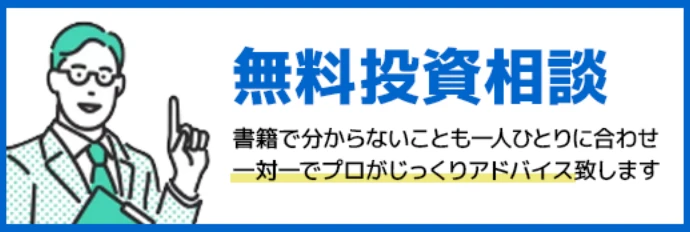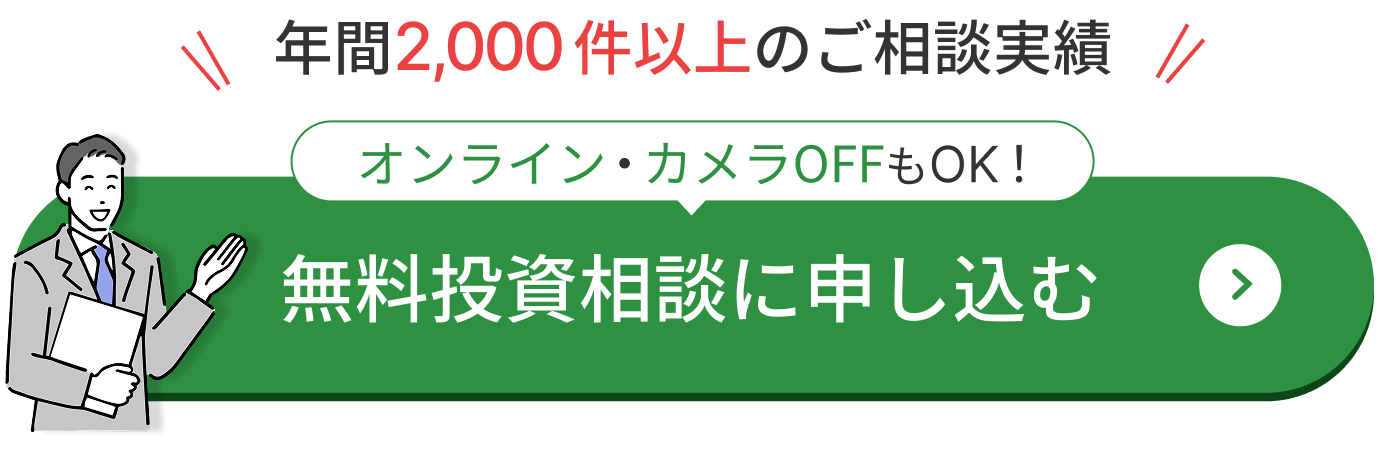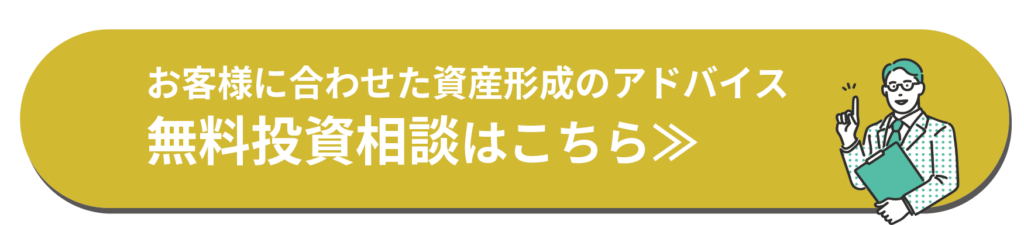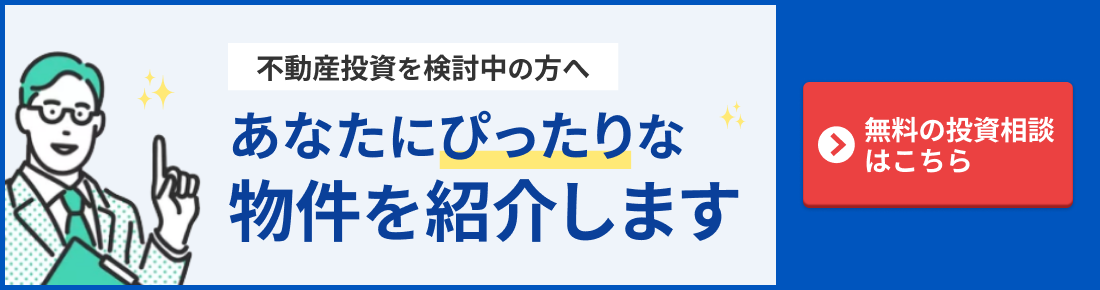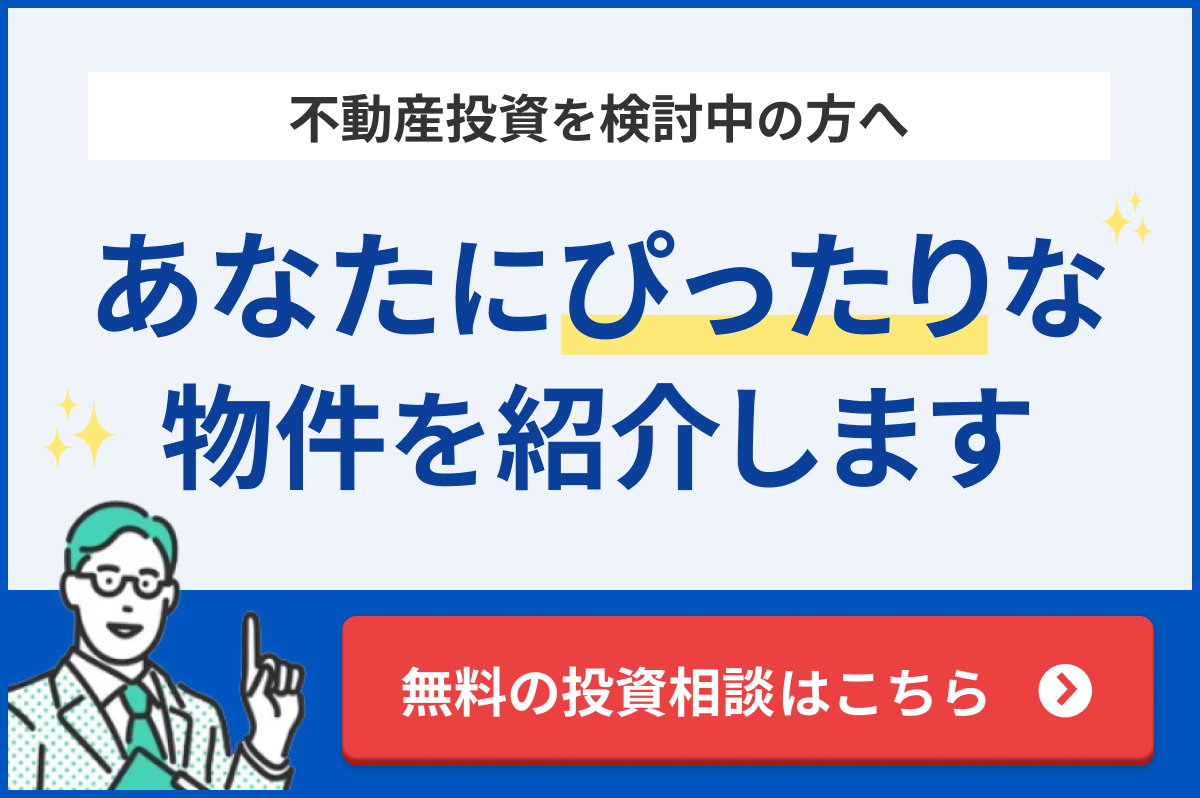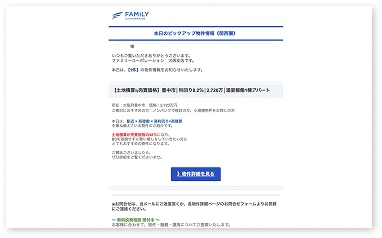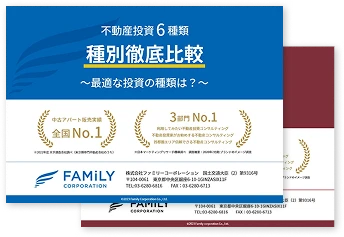マンション投資の勧誘をされたときの適切な対処方法とは?

目次
マンション投資の強引な勧誘による被害は毎年発生しており、近年は若年層にまで被害が広がっています。実際にどのような手口で勧誘され、被害が発生しているのでしょうか。
この記事では、マンション投資関連のトラブルで困っている方向けに、またこれから被害にあわないために、マンション投資の勧誘に関わる法的規制を解説します。悪質な勧誘の具体例を踏まえ、トラブルに巻き込まれた際の対処法や相談先についてもまとめました。
マンション投資では、過度な営業や誤った情報によるトラブルが後を絶ちません。
ファミリーアセットコンサルティングでは、年間400件を超える取引実績と透明性を重視した運営方針をもとに、投資初心者の方にも安心してご相談いただける環境を整えています。
無料投資相談では、投資判断に必要な正確な情報提供はもちろん、勧誘を受けた際の注意点や安全な取引の進め方についても専門コンサルタントが丁寧にアドバイス。
営業や強引な勧誘は一切行っておりませんので、安心してご利用ください。
マンション投資の勧誘とは?

マンション投資の勧誘によって、高額なマンションを契約させられるトラブルが問題となっています。
『独立行政法人国民生活センター』が運営する『PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)』によると、投資用マンションに関する20代の相談件数は年々増加傾向にあり、2013年に160件だった相談件数は、2018年には450件と大きく増加しています。
(参考: 『独立行政法人国民生活センター「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意! 」』)
具体的に、どのような苦情が寄せられているのか、法的な問題点を含めて紹介します。
よくある苦情
国民生活センターに寄せられたマンション投資に関する苦情の内容は、主に下記の通りです。
- 昼夜を問わない電話でのしつこい勧誘
- 長時間の勧誘行為、契約するまで帰そうとしない
- 強引に契約を迫られ、断ると脅された
- 契約を断ると暴力を振るわれた
- 必ず儲かるといわれて契約した後、損をした
このように、強引・脅迫的な勧誘方法が共通して問題になっています。
法的な問題点
上述のような、強引でしつこい勧誘が起こる主な理由は、マンションを含む不動産自体が高額であるからです。高額な投資商品は、なかなか成約に結びつかないため、多くの消費者にアプローチ可能な電話営業が頻繁に行われています。
マンション投資の勧誘行為、営業電話そのものは違法ではありません。しかしその勧誘方法に関しては、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)という法律の規制があります。どのような勧誘行為が違反に該当するのかについては、記事の後半で詳しく解説します。
悪質な業者への対処法と判断要素

不動産会社にの中には、宅建業法に違反した勧誘を行う業者も存在します。悪質な業者は、どのような手口で勧誘してくるのでしょうか。
悪質な業者への対処法
悪質な業者に対する基本的な対処方法は、契約する気がなければきっぱりと断ることです。また業者と直接対面しないことも重要です。
悪質な業者は、「説明するだけ」「話も聞かずに断るのはおかしい」など、勝手な理由をつけて、直接会うことを要求します。会うと断りにくい雰囲気になることを、業者側も承知しているからです。電話営業がかかってきたら、契約の意思がない旨を伝えて、それでも食い下がる場合は電話を切りましょう。
悪質な業者の判断要素
悪質な業者の判断要素としては、まず、投資リスクについて一切の説明がないことです。マンション投資にはリターンだけではなく、リスクも必ず存在します。
マンションが空室になったり、滞納が発生したりすると家賃収入が入らなくなり、建物・設備の老朽化、築年数の経過などによりマンションの価値が減少するなどのリスクがあります。こうしたリスクに一切触れないで、セールストークをする業者は信用すべきではありません。
また、マンションが高利回りかつ好立地、市場に比べて格安な販売価格など、条件がそろいすぎている場合、手付金の支払いを急かすことがあります。この場合、手付金を受け取ったあとに連絡が取れなくなる「手付金詐欺」の可能性もあるため、注意が必要です。
宅建業法の違反となるのはどんなとき?

悪質なマンション投資の営業行為は、宅建業法で規制されています。具体的にどのような行為が発生したときに、宅建業法上の違反になるのか、以下の3つの禁止事項を紹介します。
- 威迫行為の禁止
- 相手方等の利益の保護に欠ける行為の禁止
- 断定的判断の提供の禁止
威迫行為の禁止
契約を結ばせるため、または契約の解除・撤回をさせないために、脅迫による恐怖心とまではいかないまでも相手を不安にさせる行為は、宅建業法で禁止している威迫行為に当たります。刑事事件にならない程度に、相手に心理的な不安感を与える悪質な行為です。
例えば、マンション投資の勧誘を受け、一応は話を聞き、やはり断ろうとその場を断り立ち去ろうとしたところ、強引に引き止められることがあります。その場にいた複数人の営業スタッフや従業員に囲まれて契約を迫られたという事例も報告されています。これは明確な威迫行為であり、宅建業法違反と判断できます。
相手方等の利益の保護に欠ける行為の禁止
宅建業法上、「相手方等の利益の保護に欠ける行為」は禁止行為とされています。
例えば、「いま申し込まなければ絶対に損をする」などと、相手に考えさせる時間を与えずに不当に契約を結ぶことを迫るのは禁止です。「営業電話などで相手を長時間拘束する」「昼夜を問わない営業電話で相手の生活に悪影響を与える」「迷惑メールによって勧誘する」なども、相手方等の利益の保護に欠ける行為とみなされます。
実例として、対面でのマンション投資の勧誘を受け、何時間も家に帰してもらえず疲れ切った末に、契約を結んでしまったというケースがあります。執拗な勧誘電話に対しては、電話口できっぱりと断ることが重要です。
断定的判断の提供の禁止
宅建業法上、「断定的判断の提供」は禁止されています。マンション投資においての断定的判断の提供とは、不動産業者が相手に対して、将来的な収益など不確実な事柄について「将来必ず値上がりする」「利益が出ることは確実」などと断定的な判断を示し誤解させることです。
投資には、リターンに伴うリスクが必ず存在します。不動産投資に限らず、「必ず儲かる」という謳い文句の話は詐欺である可能性が高いでしょう。成功率100%の儲け話が本当であれば、わざわざ他人にスキームを紹介する必要はないでしょう。
トラブルになる前にできることポイント3つ

マンション投資についてしつこい勧誘を受けた場合、解決するにはどのような点に注意したらよいのでしょうか。ここでは、トラブルに発展する前に問題を解決する3つのポイントを解説します。
- 理由を伝えて断る
- 公的な機関に相談していると伝える
- 不動産会社の情報を調べておく
理由を伝えて断る
勧誘を断る場合は、はっきりと「契約の意思がない」と伝えることが何よりも大事です。心の中で嫌だと思っていても、契約まで至ってしまっては、後で契約の意思がなかったことを証明することは難しくなります。場合によっては会話を録音することも有効でしょう。
一度断っても勧誘を続けるのは、「再勧誘の禁止」として、特定商取引法で禁止されています。何度も同じ電話がかかってくる場合は、法的に禁止されている旨を伝えましょう。
公的な機関に相談していると伝える
こちらが契約の意思がないことを伝えたにもかかわらず止めようとしない勧誘に対しては、公的な機関や消費生活センターなどに相談することを伝えましょう。
消費者センターなどの公的機関の助言でも問題が解決しなかった場合、消費者センターと情報共有している『独立行政法人国民生活センター』の紛争解決委員会に仲裁を申請することもできます。相談が可能な各種機関に関しては、記事後半で改めて解説します。
不動産会社の情報を調べておく
悪質な勧誘行為を繰り返す不動産会社に悩まされている場合、不動産会社の情報を調べておくことも有効です。『国土交通省ネガティブ情報等検索サイト』で業者名を入力すると、行政処分を受けた宅地建物取引業者が検索可能です。また一部の都道府県のホームページでも、過去の宅地建物取引業者に対する行政処分を掲載しています。
国税庁の法人番号公表サイトから会社名を入力すると、法人番号と会社所在地を検索できます。ここで検索結果に出なかった場合、会社自体が存在しない可能性があります。またこのサイトでは、その会社の社名や住所変更の履歴も閲覧可能です。短期間に何度も社名や住所を変更しているような場合は、疑ったほうがよいでしょう。
(参考: 『国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト』)
マンション投資の勧誘の事例4つ

悪質な不動産会社は、さまざまな方法でマンション投資の勧誘を行っています。ここでは、よく見られる勧誘方法についてお伝えします。事例を知ることで、被害から身を守る対策にもつながるでしょう。
- 事例1:若者へのデート商法が増えている
- 事例2:断っても昼夜問わず電話がかかってくる
- 事例3:独自のスキームや特許申請中を語る
- 事例4:住宅ローンやフラット35を使えると提案してくる
事例1:若者へのデート商法が増えている
近年、若者へのデート商法が増えています。デート商法とは、街頭アンケートなどできっかけを作り、男女間の恋愛感情があるかのように振る舞って、高額な商品を購入させる詐欺手法です。
最近では、マッチングアプリや婚活サイトなどで知り合い、恋愛感情を利用してマンション投資の話を持ちかけるケースが増えています。恋人関係になったと思わせた上で、「二人の将来のために」などと投資マンションの購入を持ちかけるのが常套手段です。
事例2:断っても昼夜問わず電話がかかってくる
営業電話は、現在でも不動産投資の主流の勧誘方法です。断っても昼夜を問わず営業電話をかけてきたり、個人の電話だけでなく勤め先の会社にもかけてきたりするケースもあります。勧誘された側が「あまりにしつこいため」、または「勤務先に迷惑をかけるから」などといった理由で折れて、直接対面に応じることを狙っています。
対面後は強引な契約で、無理やり契約に持っていくのが常套手段です。勧誘を断ると暴力を振るうといった悪質なケースもあります。前述した通り、一度断っても勧誘を継続することは「再勧誘の禁止」として、特定商取引法で明確に禁止されています。何度も同じ電話がかかってくる場合は、相手方が違法な営業をしていることを伝え、直接会わないようにしましょう。
事例3:独自のスキームや特許申請中を語る
悪質な不動産会社の中には、「必ず儲かる」といってセミナー等の参加者からお金をだまし取る会社も存在します。
最新の事例として、「特許申請中の手法によって再現性の高い高利回りのノウハウを教える」という名目で、コンサルティング料を取った会社が訴えられました。実際には特許申請はなされておらず、特別なノウハウもありませんでした。
「うまい話には必ず落とし穴がある」と慎重になることをおすすめします。現実には、「自分はひっかからない」という自信がある方ほど落とし穴にはまる傾向があります。詐欺の手法は日々、巧妙化しているため、自分に知識・経験がない分野の儲け話には、基本的に乗らないのが賢明です。
事例4:住宅ローンやフラット35を使えると提案してくる
不動産会社の中には、「フラット35などの住宅ローンを使えば金利が低く、長期間の融資を受けられます」と、住宅ローンを使ったマンション投資を持ちかけてくる会社も存在します。
居住目的ではなく、投資目的でマンションを購入する際に住宅ローンを利用するのはローン契約違反です。うそが発覚すると一括返済が求められることになり、たとえ「不動産会社のアドバイスに従った」などと主張しても詐欺罪に当たります。おかしな提案を持ちかけられても取り合ってはいけません。
困ったときの相談窓口について

最後に、マンション投資の強引な勧誘に困っている、また勧誘を断り切れずに契約してしまった場合の相談窓口を紹介します。
- 国民生活センター
- 地方整備局や都道府県などの行政庁
- 東京都住宅政策本部
できるだけ早い段階で相談することが解決の近道となるので、一人で悩まず、まずは相談してみましょう。
国民生活センター
国民生活センターは、国が管理している独立行政法人で、全国の消費者センターと消費者相談に関する情報共有を行っています。
マンション投資に関連する業務としては、消費者センターで解決が困難だった場合の相談業務、紛争解決委員会による消費者と事業者間の紛争を「裁判外紛争解決手続」として裁判外で解決することなどがあります。
(参考: 『独立行政法人 国民生活センター』)
地方整備局や都道府県などの行政庁
不動産の売買・仲介を行う会社は、宅地建物取引業の免許が必要です。宅建業者の免許は、国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類があります。悪質な勧誘で悩まされている場合は、その不動産会社の所属する免許行政庁に相談してみましょう。
- 国土交通大臣免許業者
免許行政庁は各地方整備局などです。相談先は、その不動産会社(本店)の都道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局になります。
- 都道府県知事免許業者
免許行政庁が都道府県のケースでは、該当する都道府県の宅地建物取引業免許部局に相談しましょう。
東京都住宅政策本部
都道府県によっては、独自の相談窓口を設置しているところもあります。例えば東京都のマンション投資トラブルに関しては、東京都住宅政策本部があります。宅地建物取引業法の規制対象の疑いがある場合は相談してみるとよいでしょう。個人に限り、不動産取引紛争等の民事上の無料法律相談もできます。
(参考: 『東京都住宅政策本部』)
まとめ
いまだに悪質な手口でマンション投資の勧誘をしてくる不動産会社が存在します。もっとも効果的な対処法は、悪質な不動産会社の特徴を把握し、怪しいと思ったら一切取り合わないことです。よくある事例をチェックし、常套句や常套手段を知っておきましょう。
ファーストコンタクトで見抜けなかったとしても、悪質なマンション勧誘だと感じたらきっぱりと断ることが重要です。契約する意思がないと断ったにもかかわらず勧誘が続くようであれば、各種公的機関や宅地建物取引業の免許を管轄する行政庁に相談することをおすすめします。
監修者プロフィール