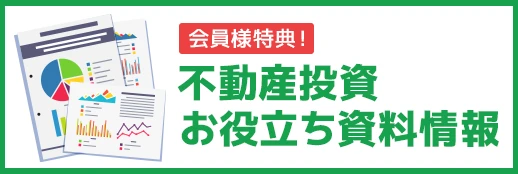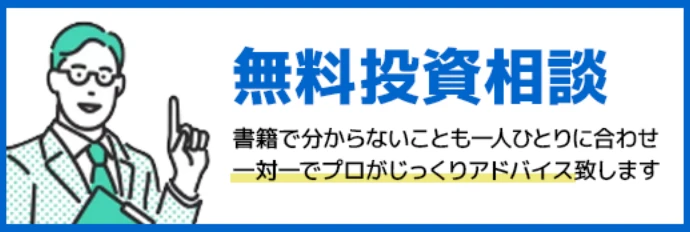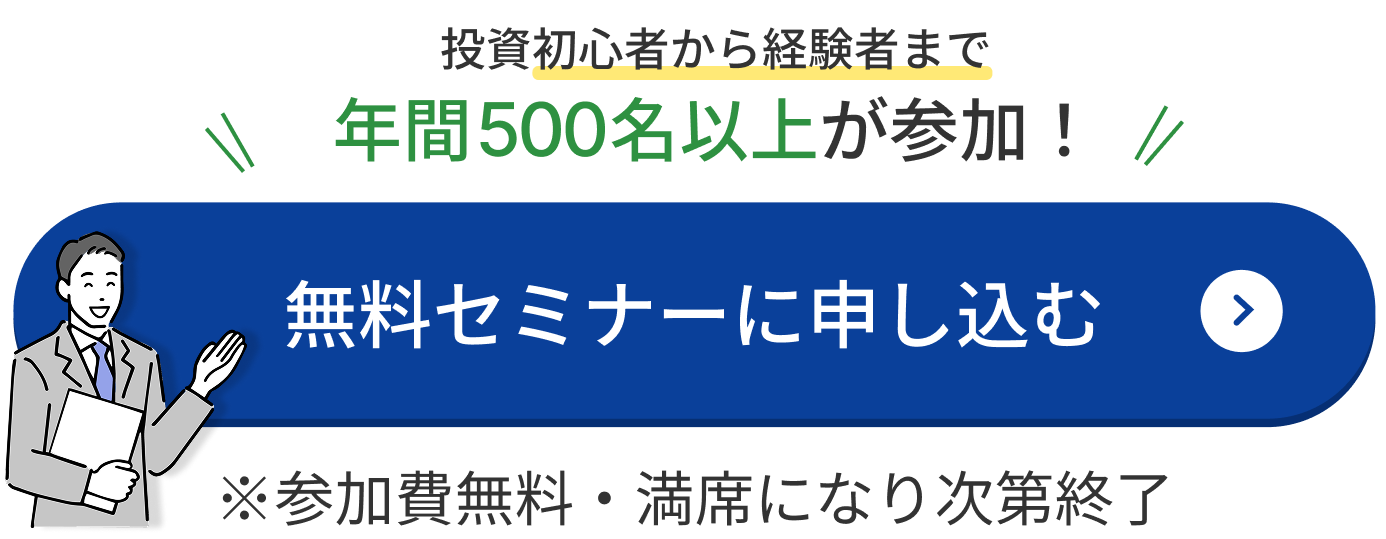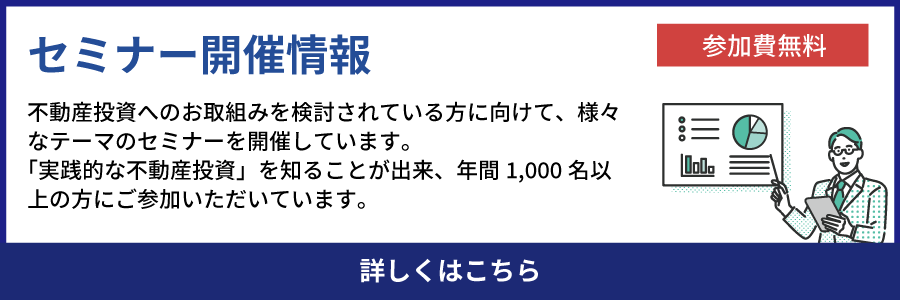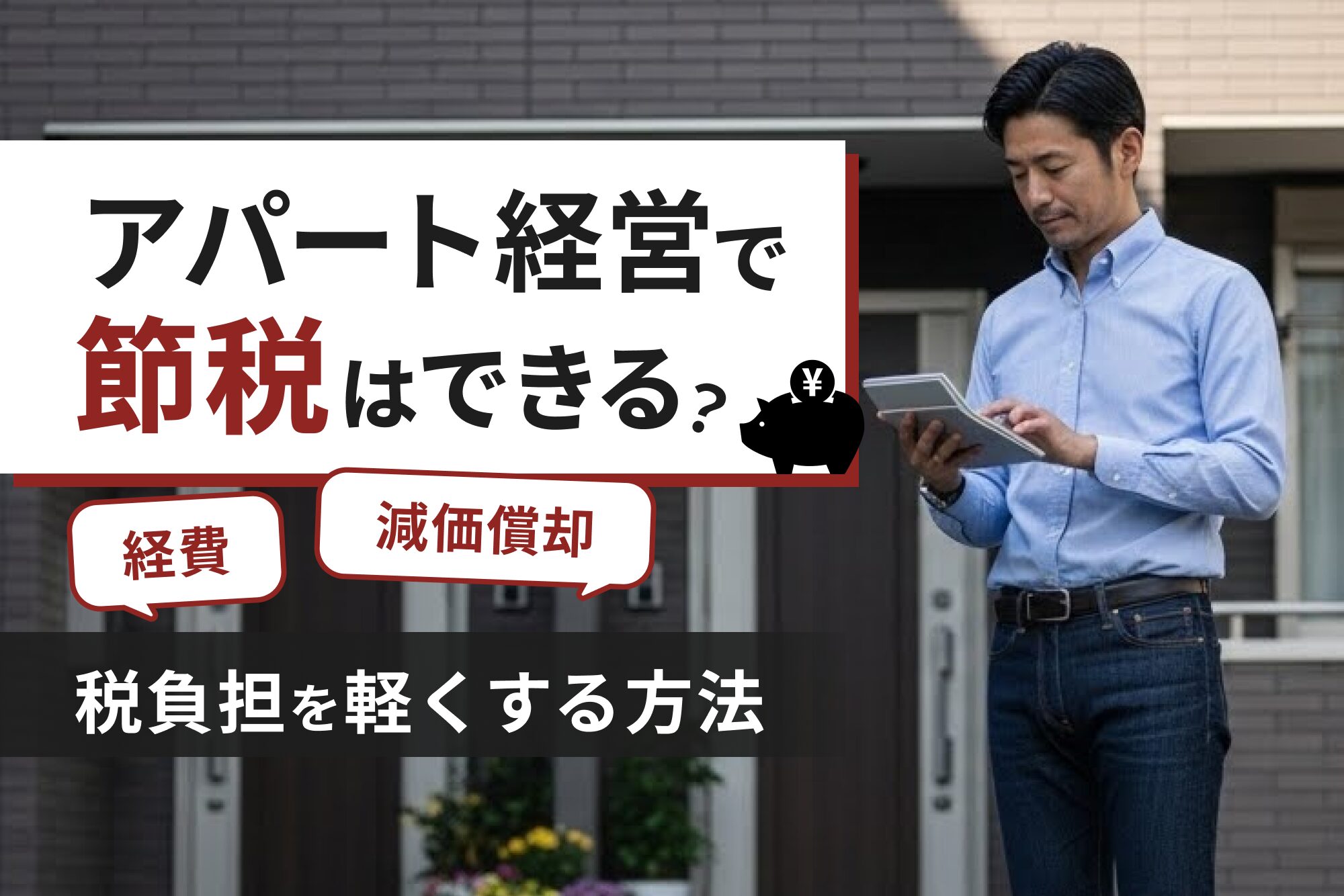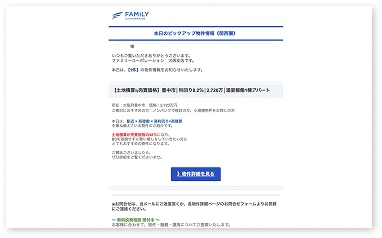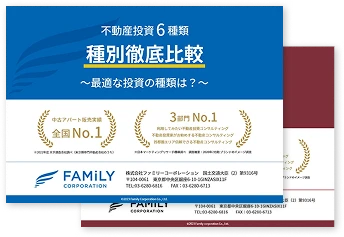不動産所得に確定申告は必要?計算方法や必要書類などを詳しく解説

目次
確定申告とは1年間の所得に対して課せられた税金を国に自己申告する手続きです。確定申告のルールは複雑であるため、不動産投資を行っていると「確定申告が必要なのか?」「確定申告の計算方法は?」と気になる方は多いかと思います。
不動産投資を行ううえで確定申告はほとんどの方が必要となるため、計算方法や必要書類、流れなどをおさえておくのが大切です。
本記事では確定申告が必要となるケースや計算方法、申告までの流れを紹介します。不動産投資を行っている方はぜひ本記事を参考にしてみてください。
確定申告の仕組みを正しく理解することで、節税効果を最大化し、収益を守ることが可能です。
ファミリーアセットコンサルティングでは、税務や経費計上の基礎から実践まで学べる無料投資セミナーを定期開催しています。
セミナーでは、実際の申告事例や注意点を税務の専門家がわかりやすく解説。
さらに、非公開の高利回り物件(8%以上)の紹介や、個別相談の特典もご用意しています。
「確定申告のポイントを理解して無駄なく節税したい」という方は、ぜひ無料セミナーにご参加ください。
そもそも不動産所得とは

不動産所得とは所得税法によって10種類に区分された所得のひとつであり、不動産の総収入金額から必要経費を差し引いた金額を確定申告します。10種類の所得は以下の表の通りです。
| 利子所得 | 預貯金および公社債の利息貸付信託や公社債投資信託などの収益分配 |
| 配当所得 | 株式配当投資信託および特定受益証券発行信託の収益分配出資の剰余金分配 |
| 不動産所得 | 不動産(土地や建物など)不動産の上に存する権利(借地権・地上権など)船舶および航空機の貸付 |
| 事業所得 | 農業漁業製造業卸売業小売業サービス業その他の事業 |
| 給与所得 | 勤務先から受け取る給料や賞与 |
| 退職所得 | 退職手当退職一時金 |
| 山林所得 | 山林を伐採して譲渡・もしくは立木のままの譲渡により生じる所得(山林は5年を超えて所有していることが条件) |
| 譲渡所得 | 資産の譲渡および地上権などの設定により生じる所得 |
| 一時所得 | 上記8所得のいずれにも該当せず、対価としての性質を持たない一時的な所得 福引や懸賞の賞金競輪や競馬の払戻金生命保険の一時金損害保険の満期返戻金 など |
| 雑所得 | 上記9所得のいずれにも該当しない所得 公的年金原稿料講演料印税非営業用貸金の利子 |
3種類の不動産所得のうち、地上権とは借地などを他人に貸して得る地代収入を指します。不動産や船舶・ 航空機などの貸付けによる収入も不動産所得に含まれます。
不動産所得の確定申告はした方が良い

給与以外の所得が20万円を超えている場合は確定申告する必要があります。そのため、不動産投資を行っているほとんどの方は確定申告を行う必要があるとおさえておきましょう。
また、不動産所得が20万円以下である場合は確定申告は義務ではありませんが、行った方が良いとされています。次の項目から詳しく紹介していきます。
不動産所得が20万円以下の場合は確定申告が不要
不動産所得は「 総収入金額 - 必要経費」の式で算出されます。不動産所得が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりませんが、20万円以下の場合は義務ではありません。一方で、20万円を超えていなくても確定申告をすることでメリットがあります。
不動産投資の収入金額と必要経費として認められる項目は以下の表の通りです。
| 不動産投資における収入 | ・家賃収入 ・共益費 ・更新手数料 ・礼金 |
| 不動産投資における経費 | ・固定資産税 ・損害保険料 ・減価償却費 ・修繕費 など |
不動産投資の際は必要経費にできる項目をもれなく経費計上するのがポイントです。
不動産所得が赤字になった場合、給与所得や事業所得などの所得から赤字分を相殺(損益通算)し、課税所得をおさえることで節税効果が得られます。
不動産投資の場合、物件の取得費を毎年分割して経費計上できる減価償却を行えるため、会計上の赤字を発生させやすく、損益通算につなげやすいといえます。また、あくまでも帳簿上の赤字であるのがポイントであり、実際の支出を伴わずに節税効果が得られます。
なお以下に挙げる不動産損失は損益通算の対象にならないため、注意が必要です。
- 主に趣味、娯楽、保養、鑑賞の目的で所有する、通常の生活に不要な不動産の貸付に関する物件(別荘など)
- 不動産所得に含まれる土地などを取得するための借入金利子相当金額
損益通算ができる項目とできない項目をしっかり区別したうえで、確定申告に必要な計算をしましょう。
不動産投資以外で確定申告をした方が良い場合
不動産投資以外でも、確定申告をした方が良い場合もあります。不動産投資以外では主に以下のケースでは手続きをしたほうが良いとされます。
| 手続きした方が良い場合 | 概要 |
| 医療費が10万円を超える場合 | 医療費で発生した支出を所得から控除できる |
| 寄附やふるさと納税をした場合 | ふるさと納税額から2,000円を指し引いた金額に税率を掛けた値を所得から控除できる |
| 住宅ローンを組んだ場合 | 「残債 × 0.7%」が所得から控除できる ※ローンを組んで13年以内かつ年収2,000万円未満の方が対象 |
上記に該当するケースが所得税の節税効果につながるため確定申告を行うようにしましょう。
確定申告の計算方法

確定申告は総収入金額から必要経費を差し引いて計算したのち申告を行います。確定申告は以下の流れで行います。
- 不動産所得を単体で算出する
- 不動産所得と給与所得は合算して確定申告する
確定申告の計算方法を次の項目から解説します。
不動産所得を単体で算出する
最初に不動産所得単体を以下の計算式で算出します。
所得金額 = 総収入金額 - 必要経費
総収入金額には貸付けによる賃料収入のほかにも礼金や更新手数料、更新費、共益費などが含まれます。
必要経費は不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できる部分であり、主に以下の項目が該当します。
- 減価償却費
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料・地震保険料
- 借入利子
- 不動産の光熱費
- 管理委託手数料
- 清掃費
- 修繕費用など
計算式を使って所得金額が計算できたら、次のステップに進みます。
不動産所得と給与所得は合算して確定申告する
不動産所得を算出できれば、給与所得と合算して確定申告を行います。 不動産所得はすべての所得の合計金額を課税対象とする総合課税であるため、上記で解説した所得金額に給与所得を合算した金額で確定申告を行います。
また総合課税とは別に、所得ごとで課税額を計算する分離課税もあります。分離課税の対象は他の所得とは合計せず、単独で申告する必要があるため注意が必要です。分離課税には譲渡所得・山林所得・退職所得などが含まれます。
不動産所得の確定申告をする際の必要書類

不動産所得を確定申告するには以下の6種類の書類が必要です。
| 書類名 | 書類の内容 | 提出先 |
| 確定申告書B(第一表・第二表) | 個人事業主向けの確定申告書 | 税務署 |
| 青色申告決算書不動産用(青色申告を行う場合) | 不動産所得の明細書 | 税務署 |
| 収支内訳書不動産用(白色申告を行う場合) | 収入金額や仕入れ金額の明細を記入した用紙 | 税務署 |
| 収入が分かるもの (現金出納帳・契約書・通帳など) | 青色申告決算書もしくは収支内訳書の作成に必要 | 提出不要 |
| 賃借人の氏名や月額の家賃などが分かる資料(送金明細など) | 同上 | 提出不要 |
| 必要経費が分かるもの (借入金支払明細、銀行振込書、固定資産税領収書など) | 同上 | 提出不要 |
上記6種類の書類を含め、確定申告に必要な書類と入手先は以下の表の通りです。
| 入手先 | 書類 |
| 税務署、国税庁Webページ、会計ソフトなど | 確定申告書B 不動産所得用の青色申告決算書 収支内約書(白色申告の場合) |
| 勤務先 | 源泉徴収票 |
| 不動産会社・管理会社など | 不動産売買契約書 不動産を売買した際の費用が分かるもの(売渡精算書など) 譲渡対価証明書 賃貸契約書 家賃が送金された際の家賃明細書 |
| 不動産ローンの借入先 | 不動産ローンの返済予定表 |
| 行政から送付 | 固定資産税、都市計画税の通知書 |
| 自身で用意 | マイナンバーカード納税通知書の控え |
上記の表から確定申告には多くの書類が必要であるため、準備漏れがないよう十分注意しましょう。なお、作成した帳簿は7年間の保存が義務付けられています。
確定申告の流れ
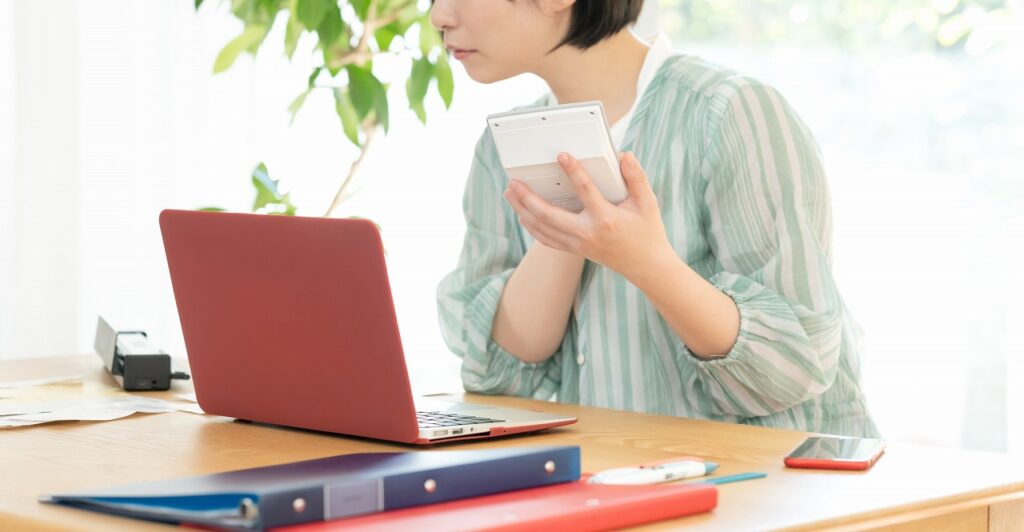
確定申告は前年に発生した所得や経費から所得税を算出し、毎年2月16日から3月15日までに税務署へ申告書類を提出します。期限までに確定申告を行わないとペナルティを受けてしまう可能性があるため、必ず行うようにしましょう。
確定申告は以下の流れで手続きを進めます。
- 書類を準備する
- 申告書を作成する
- 申告書を提出する
- 納税する・もしくは還付を受ける
それぞれのステップについて紹介していきます。
書類を準備する
「不動産所得の確定申告をする際の必要書類」の項目で解説した書類を準備します。書類以外にも、マイナンバーカード及びマイナンバーが記載された住民票なども用意しましょう。
書類が準備できたら、前回の確定申告以降に記録していた帳簿を整理し、売上や支出などの入出金記録を確認します。書類はすべて帳簿を基にして作成するため、普段からこまめに記録することが重要です。
申告書を作成する
書類と帳簿の内容を照らし合わせながら申告書を作成します。作成方法は以下の4通りから選択可能です。
- 手書きおよび手計算により自分で作成する
- 確定申告ソフトを使い自分で作成する
- 税理士に依頼する
- 国税庁のウェブサイト内にある確定申告書等作成コーナーを利用する
記入する際には数字を書き間違いないよう慎重に行いましょう。
申告書を提出する
申告書の作成が完了し添付書類の準備ができたら管轄する税務署へ提出します。提出方法は、以下の4通りから選択可能です。
- 税務署に直接持参する
- e-taxを利用する
- 郵便もしくは信書便で税務署へ郵送する
- 税務署の時間外収受箱へ投函する
税務署が推奨している方法は e-Taxです。初めて利用するときには、開始届出書を提出し利用者識別番号を受け取ります。
納税する・もしくは還付を受ける
申告書の提出後、以下5通りの方法から選択して納税を行います。
- ダイレクト納付
- インターネットバンキング等を利用する
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- 振替納付
還付金がある場合は申告書に記載した金融機関口座へ後日振り込まれます。
不動産投資の正しい知識を身に付けることが大切
不動産投資には投資だけでなく税務に関する知識が必要となります。税務に関する疑問などがあれば税理士にサポートを依頼できますが、自分自身でもある程度は正しい知識を身につけておくことが大切です。
自身で知識を身につけるには、不動産投資セミナーに参加し情報を得るのがおすすめです。セミナーによっては講師に直接質問できるケースもあるため、生の声が聞ける絶好のチャンスでもあります。積極的に参加して不動産投資についての知見を深めましょう。
まとめ
不動産投資によって20万円以上の不動産所得が発生した場合、確定申告を行わなければなりません。そのため、不動産投資を行うほとんどの方は、確定申告を行う必要があるとおさえておく必要があります。一方で、確定申告を行う義務がないにしても、行うことで損益通算による税金の還付を受けられる場合があります。
また、確定申告が必要な条件に該当しているにも関わらず、3月15日の期限までに申告手続きを行わないと、申告漏れとみなされペナルティを課せられる場合があります。
不動産投資や確定申告に関する知識は本などでも得られますが、セミナーに参加するのもひとつの手段です。積極的に参加し、知識を深めましょう。