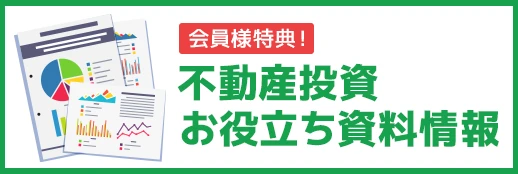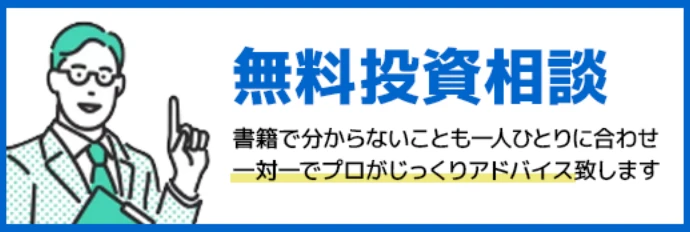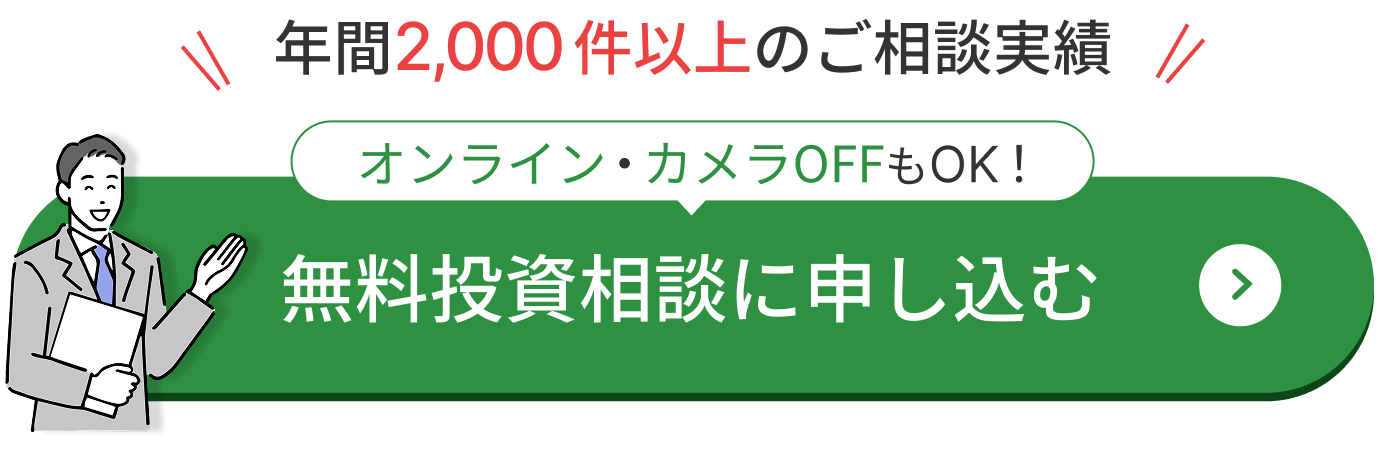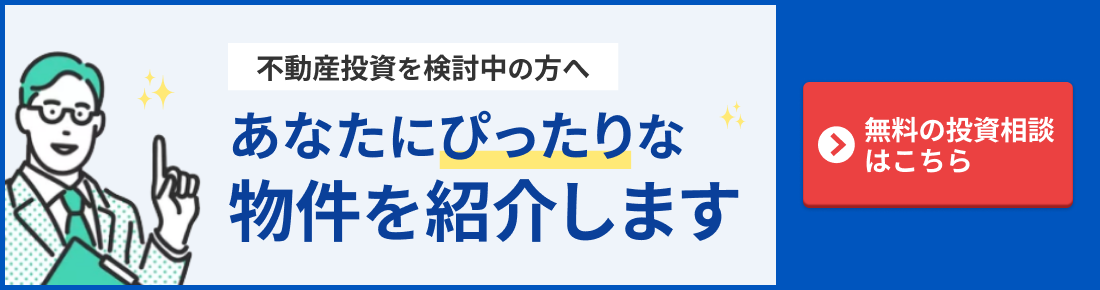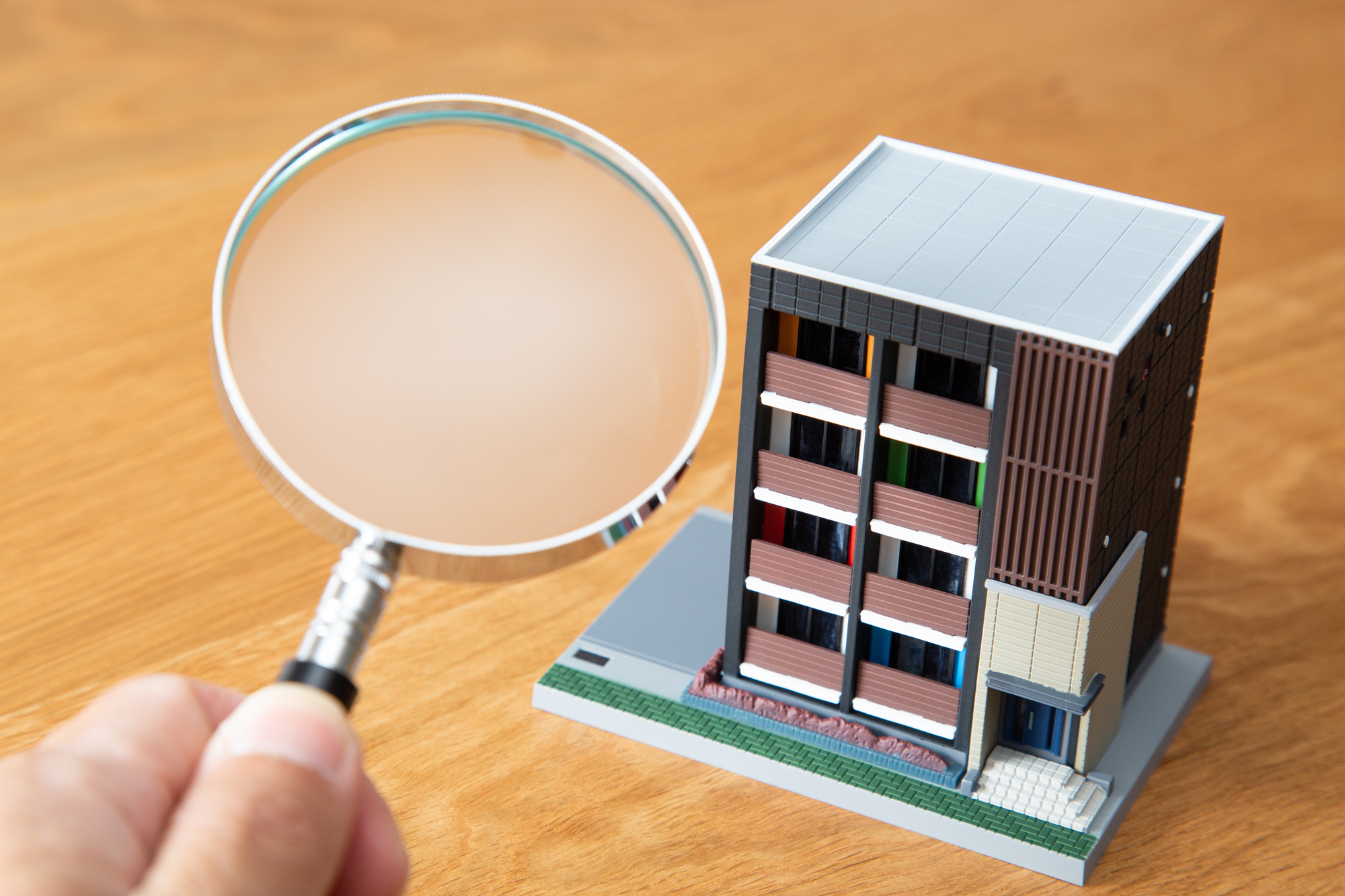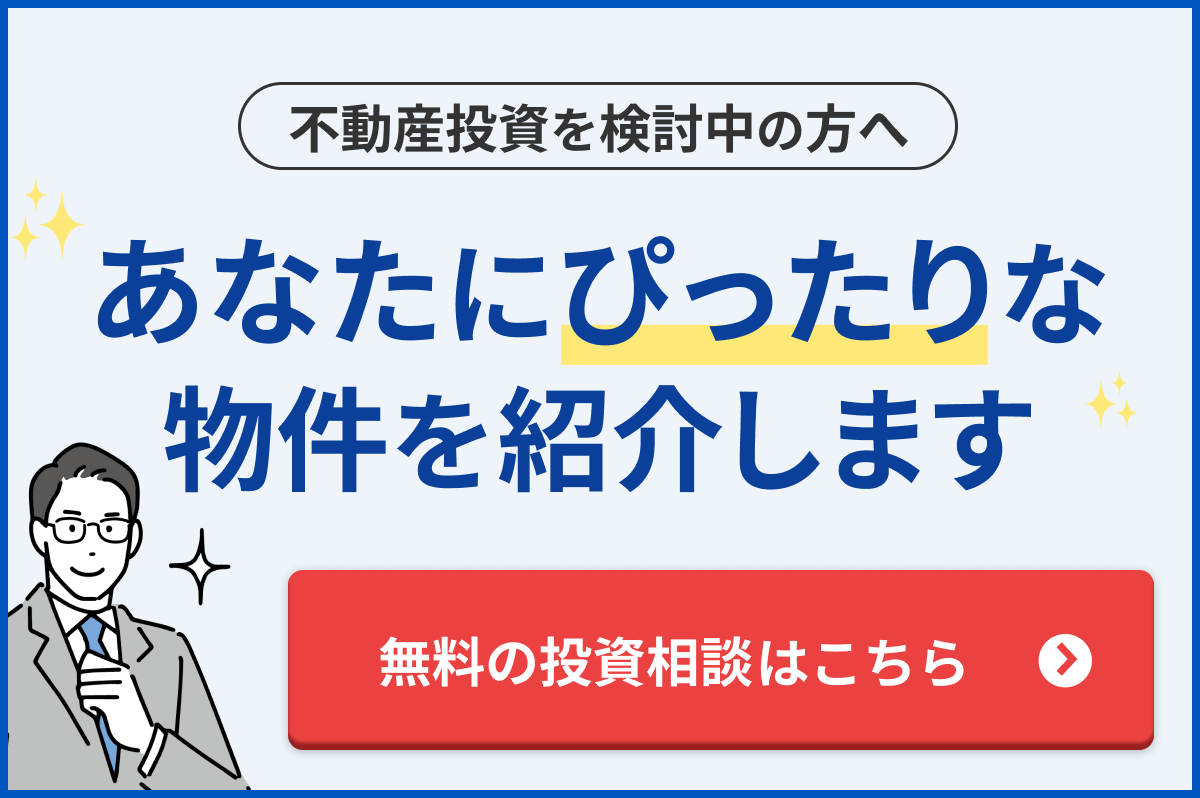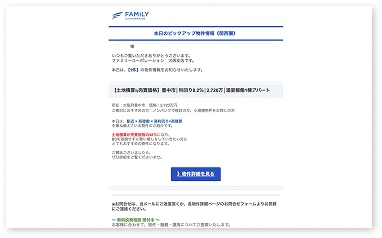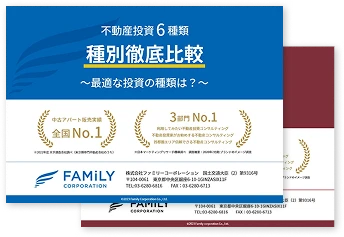ビル経営の基本と高利回りの条件とは?メリット・リスク・注意点も解説

目次
ビル経営は、高い利回りや安定収入を期待できる不動産投資の一つとして注目されています。しかし、その分初期費用や管理コストも大きく、誰でも気軽に始められるわけではありません。成功するためには、経営の仕組みや物件の種類、必要な資金、リスク管理の方法まで正しく理解することが欠かせません。
本記事では、ビル経営の基本からメリット・デメリット、向いている人の特徴、始め方のパターンまでを体系的に解説します。
ビル経営は大きなリターンを狙える一方で、初期費用・空室リスク・管理コストなど慎重な判断が欠かせません。
ファミリーアセットコンサルティングでは、投資目的や資金規模に応じて、
無理のない資金計画と最適な投資戦略をプロのアドバイザーが無料でご提案しています。
収益シミュレーションやリスク整理も丁寧にサポートするため、
初めて大規模投資を検討する方でも安心して相談できます。
「ビル経営を視野に入れつつ、最適な投資戦略を知りたい」という方は、今すぐ無料投資相談をご利用ください。
ビル経営の基本と特徴

ビル経営は長期的な安定収入を目指せる一方で、高額な初期投資や専門的な管理が求められるため、他の不動産投資とは異なる視点と準備が必要です。ここでは、ビル経営の基本的な仕組みや種類、必要な費用などについて、具体的に解説します。
ビル経営とは何か:アパートやマンション経営との違い
ビル経営とは、オフィスや店舗などのテナントに建物を貸し、賃料収入を得るビジネスモデルです。アパート経営に比べて規模が大きく、複数階建ての構造が一般的で、区画ごとに賃貸する形式が多く見られます。
主にビジネス利用を想定しているため、住宅よりも高額な賃料を設定できるのが特徴です。さらに、光熱水費を別途請求できるほか、内装の原状回復費用をテナント側が負担するケースも少なくありません。
一方で、景気の変動に左右されやすく、テナントの業績がビル収益に直接影響を及ぼすというリスクもあります。また、受変電設備や全館空調、防犯設備など、高度な設備の導入が求められます。
このような背景から、都市部や駅近、大通り沿いなど、ビジネスニーズに合った立地を選定することが、ビル経営においては非常に重要です。
ビル経営の種類と特性:オフィス・商業・複合型・医療ビル
ビル経営にはさまざまなタイプがあり、それぞれに特有のメリットや特性があります。
- オフィスビル
企業の業務拠点として利用されるのがオフィスビルです。執務スペースや会議室などを備えた構造になっており、初期費用を比較的おさえやすい上、入居期間が長期にわたる傾向があります。そのため賃料も安定しやすく、収益の見通しが立てやすい特徴があります。
- 商業ビル
飲食店や物販店など、店舗系のテナントが中心となる施設です。集客力のある店舗が入居することで人の流れが生まれ、周辺地域の活性化にもつながる可能性があります。
- 医療ビル
クリニックや診療所などを想定して設計された施設で、バリアフリー対応や衛生面への配慮がなされています。医療機関は景気に左右されにくく、一度入居すると長期にわたって利用されやすいため、退去リスクが低く安定した収益が見込めます。また、高齢化社会により、今後さらに需要の拡大が期待される分野でもあります。
- 複合ビル
一つの建物にオフィス・商業・医療など複数の機能を組み合わせた形式です。異なる業種のテナントが集まることで、施設全体の集客力を高めるとともに、相乗効果による経営の安定が期待されます。
ビル経営に必要な初期費用と維持管理コスト
初期費用はビルの規模によって大きく異なりますが、小規模な物件で数千万円、大規模になると数億円にのぼるのが一般的な目安です。
| 項目 | 内容・計算方法 |
| 建築費 | 坪単価 × 延べ床面積 |
| 諸経費 | 建築費の10% |
| 構造 | 坪単価 (万円/坪) |
| SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 約224万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 約205万円 |
| S造(鉄骨造) | 約134万円 |
(参考: 『建築着工統計調査報告(令和6年度計分)|国土交通省』)
例えば、70坪ほどの4階建てビルでは、建設費と諸費用を含めて約1億円〜1億7,000万円程度の初期投資が想定されます。
維持管理費には日常清掃、設備の保守点検、修繕、機器更新などが含まれ、年間で収入の約20%程度がかかることが一般的です。
さらに、将来的な大規模修繕や法定点検への対応も見据え、修繕積立金をあらかじめ確保しておくことが重要です。こうした継続的な支出に備えるためにも、長期的な資金計画の立案は不可欠です。
ビル経営のメリット

不動産投資の中でも、ビル経営は収益性の高さや資産活用の柔軟さから、多くの注目を集めています。単なる賃貸収入にとどまらず、土地の有効活用や相続税対策といった観点からも多くの利点があり、長期的な資産形成に適した選択肢といえるでしょう。
ここでは、ビル経営が持つ具体的なメリットについて、3つの視点から詳しく見ていきます。
高い収益性と利回りが期待できる
ビル経営は、居住用不動産に比べて賃料を高く設定できるため、収益性が高いことが大きな魅力です。特にビジネス利用を前提とした物件では、使用頻度が高く建物の摩耗も早くなることから、その分賃料を高めに設定しやすい傾向があります。
商業ビルは建築計画の自由度が高く、土地の特性に合わせて柔軟な活用ができる点が特徴です。また、複合ビルでは用途の異なるテナントを組み合わせることで、収益源を多様化し、安定した利回りを実現しやすくなります。例えば、1階に店舗を配置し、上層階にオフィスやクリニックを設けるといったレイアウトは、収益性向上の一例として効果的です。
ただし、高い収益を維持するには、空室リスクや市場環境の変動といった不確実性への備えが欠かせません。立地の選定、テナントニーズの把握、そして適切な物件管理が極めて重要なポイントとなります。
土地の有効活用が可能
ビル経営は、限られた敷地でも収益を最大化できる土地活用法として有効です。例えば、狭小地や変形地であっても、上階を活用することで収益の確保が可能となります。
また、住宅には適さない立地であっても、商業施設や医療機関などのテナントニーズが見込める場合があり、収益物件として成立する可能性があります。
さらに、容積率を最大限に生かして建築計画を立てることで、土地の資産価値を効果的に引き出すことも可能です。特に都市部などの高額な土地においては、限られた面積を効率よく活用する手段としてビル経営は適しています。
平屋や駐車場としての利用と比較しても、収益性・資産効率の面で大きな優位性がある点は、ビル経営の大きな魅力といえるでしょう。
相続税対策として有効
ビル経営は、資産活用と相続税対策を両立できる手段の一つです。賃貸用のビルを建てると、その土地は「貸家建付地」として扱われます。。所有者が土地を自由に利用できない状態とされるため、相続税を計算する際の評価が下がる仕組みです。
例えば自用地評価額が1億円で、借地権割合が70%、借家権割合が30%としましょう。この場合、「1億-(1億×0.7×0.3)=7,900万」という計算式になり、相続税評価額が約2割下がります。
また、「小規模宅地等の特例」を活用すれば、最大730㎡までの土地について評価額を8割減額することも可能です。さらに、建物自体の相続税評価額は、建築費のおよそ5〜6割におさえられるため、実際の支出よりも低く評価される傾向があります。
(参考: 『No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)||国税庁』)
郊外であっても、一定の収益性が見込めるケースがあります。自動車利用が前提となるため、駐車スペースを確保したまま上部空間を店舗やオフィスに活用すれば、来客利便性を維持しつつ、賃料収入の柱が増えます。貸家建付地としての評価減効果も得られ、節税と収益性の両立を図れるでしょう。
ビル経営のリスクと対策

収益性や資産活用の面で多くの利点を持つビル経営ですが、その一方で、空室や老朽化、災害といったさまざまなリスクも抱えています。こうしたリスクに正面から向き合い、事前に備えることが、安定した経営を継続するための鍵となります。
空室リスクと景気変動リスク
空室リスクや景気変動による影響は、ビル経営において最も大きな懸念点です。これらのリスクに適切に対応するためには、まず物件の築年数や立地、設備の状態を正確に把握し、現状を分析することが重要です。
空室対策としては、テナントのニーズに応じた改修や設備投資が効果的です。例えば、自由にレイアウト変更ができる間取りの設計や、共有スペースの充実などが入居の動機につながることがあります。
また、市場の賃料相場をふまえて適正な賃料を設定することも、安定した入居率を保つ上で欠かせません。さらに、異なる業種のテナントを組み合わせることで、不況時にも特定業種の影響を受けにくくする工夫が可能です。
募集活動については、リーシング(テナント募集)に強みを持つ不動産会社と連携することで、より効果的なテナント誘致が期待できます。
老朽化リスク
ビルの資産価値を維持していくためには、老朽化への対策と計画的な大規模修繕が欠かせません。長期修繕計画は、30年以上のスパンを想定し、その間に2回以上の大規模修繕を盛り込むことが望ましいとされています。
計画には、外装や設備、共用部の修繕内容を具体的に示し、必要となる費用も明確にする必要があります。修繕積立金については、将来の工事費総額を下回らないよう、着実に確保しておくことが基本です。
また、修繕計画は5年ごとを目安に見直し、建物の現況や周囲の環境変化に応じて柔軟に更新しましょう。専門家による定期的な調査も依頼し、劣化の進行状況を把握した上で、適切な時期に必要な修繕を実施することが重要です。
災害リスク
地震や風水害などの自然災害は、建物の損壊だけでなく、家賃収入が入ってこなくなるといった経営面にも直接的な影響を及ぼします。そのため、火災保険・地震保険はもとより、家賃補償特約の検討も重要です。
ビルの用途や設備に応じて、施設賠償責任保険や動産総合保険など、適切な補償内容を選ぶことも求められます。
なお、古い火災保険では風災・雹災・雪災の補償が不十分な場合があるため、契約内容を確認しておきましょう。ハザードマップや専門家の意見を参考にしながら、保険の見直しを定期的に行うことが、万一の損害を最小限にとどめるための鍵となります。
ビル経営に向いている人の特徴と適性
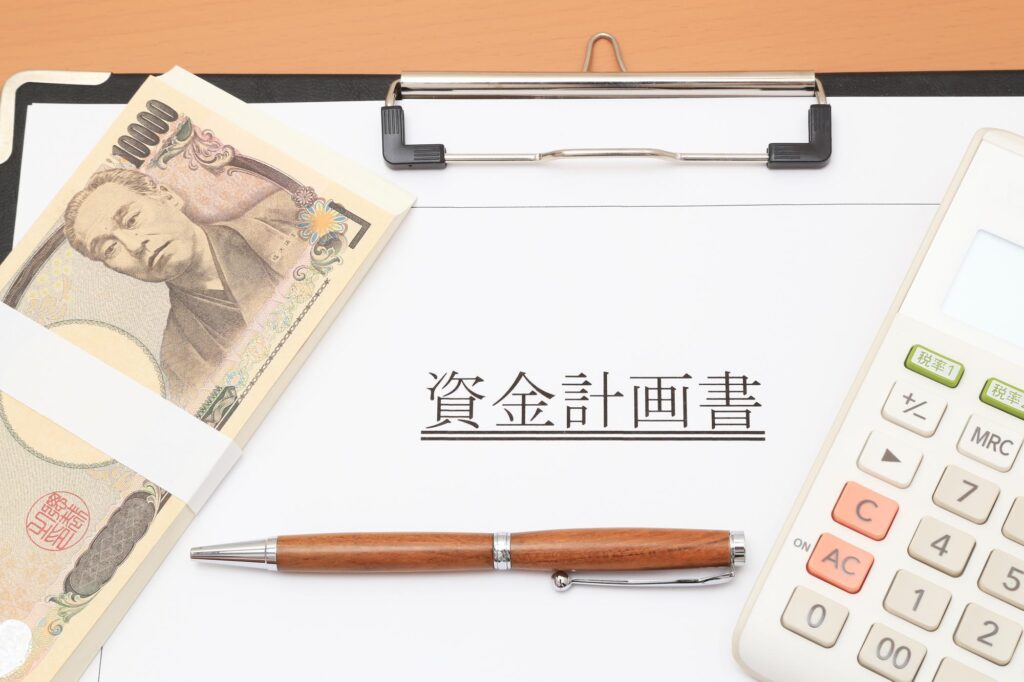
ビル経営は高い収益性が期待できる一方で、初期投資や運営にかかる負担も大きいため、誰にでも適しているとは限りません。成功するためには、資金面だけでなく、立地条件や専門家との連携といった多面的な要素が重要です。
自己資金が十分に確保できる人
第一に、十分な自己資金の確保が前提となります。空室期間が発生しても安定して経営を続けるためには、資金に余裕があることが大切です。また、自己資金の比率が高いほど、金融機関から有利な融資条件を引き出しやすくなる傾向があります。
人通りが多い場所や駅近の土地を所有している人
駅から徒歩10分以内、できれば7〜8分以内でアクセスできる立地は、テナントからの需要が高く、空室リスクをおさえることにつながります。。人の流れが多い場所であれば、オフィスや店舗、クリニックなどさまざまな用途に対応しやすく、安定した賃貸収入が期待できます。
また、ビジネス街や商業エリア、再開発が進んでいる地域など、将来的に資産価値の上昇が見込まれる土地も、ビル経営に適しています。立地の利便性だけでなく、周辺にコンビニや飲食店、医療機関といった施設が整っているかどうかも重要です。こうした環境はテナント募集のしやすさと、入居後の顧客誘引力の両方に影響します。
すでにこうした条件に合致する土地を保有している場合は、初期投資をおさえながらも高収益を目指したビル経営が検討できるでしょう。。
ビル経営を始める3つの方法

ビル経営を始めるには、大きく分けて「土地を活用して建設する」「既存のビルを購入する」「相続物件を活用する」という3つの方法があります。いずれの方法も、それぞれに異なるメリットや注意点があり、自身の状況や資金計画に応じた選択が求められます。
最後に、各方法の特徴と検討すべきポイントについて解説します。
所有している土地にビルを建設する
所有地にビルを建設する方法は、立地や用途地域、周辺の需要を的確に見極めれば、高い収益性が見込める選択肢です。商業エリアや駅近など、テナントニーズの高い場所であれば、安定した賃貸収入を得られる可能性があります。
メリットとして、土地取得費が不要な分、初期費用をおさえられ始めやすい点が挙げられます。また、エリアの需要に合わせたテナントの業種や用途に合わせて、間取りや設備を自由に設計できることも利点です。
一方、建築には融資、設計、申請など多くの工程が関わり、計画力が求められます。建築費の高騰や賃料設定の誤りが収益悪化を招く恐れもあります。
特に重要なのは、賃料相場や空室リスクの精査です。地域の動向や競合状況を見誤ると、安定した賃貸収入を得ることが難しくなります。駅近や人通りの多い土地を所有している場合は、有利に進められる可能性が高いといえます。
中古の一棟ビルを購入する
すでに建っているビルを一棟まるごと購入する方法は、中古物件を対象とするケースが一般的で、立地、築年数、管理状態を丁寧に見極める必要があります。物件によっては割安に購入できる可能性があり、表面利回りが一定水準を満たせば、自己資金が少なくても融資を受けやすくなります。
大きなメリットは、取得後すぐに賃貸収入を得られる可能性がある点ですが、建物の老朽化や修繕履歴を事前に確認しておかないと、後から修繕費や管理費などの見えないコストが発生するリスクがあります。
空室率や利回りの過去実績を必ず確認し、収支の見通しを立てることが重要です。初心者は独断で判断せず、不動産会社や建築・管理の専門家と連携し、慎重に物件を選びましょう。
相続したビルを活用する
相続したビルを活用する場合、すでに所有している不動産を使うため、新たに土地や建物を購入する必要がなく、初期費用を比較的おさえられるのが大きな利点です。また、築年数や過去の使用状況を事前に把握しやすいため、見通しを立てやすいというメリットもあります。固定資産税の負担軽減や、相続税対策としての活用ができる点も見逃せません。
ただし、建物が古い場合は、耐震性や設備面で基準を満たさないこともあり、大規模なリノベーションや修繕が必要になるケースがあります。あらかじめ現況を調査し、修繕費用や工期を含めた事業計画を立てましょう。
また、登記の未整理や、相続人が複数いる共有状態の場合には、売却や賃貸の意思決定に時間を要し、運用に制約が出る可能性もあります。ビルが「眠った資産」とならないよう、テナントの見直しや用途変更を通じて、収益率の工場に向けた活用を検討することが良いでしょう。
まとめ
ビル経営は、高い収益性や土地の有効活用、相続税対策といったメリットがある一方で、景気に左右されやすいことや、空室リスクの高さなどのデメリットも伴います。
不動産投資にはさまざまな種類があり、取り組む人の資産状況に応じて、適した物件と避けるべき物件が存在します。こうした特性を理解することで、不動産投資の成功に近づくことができます。
アパート・マンション等経営とビル経営の違いを正しく把握し、今後の投資判断に役立てましょう。
監修者