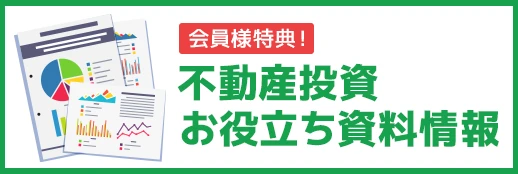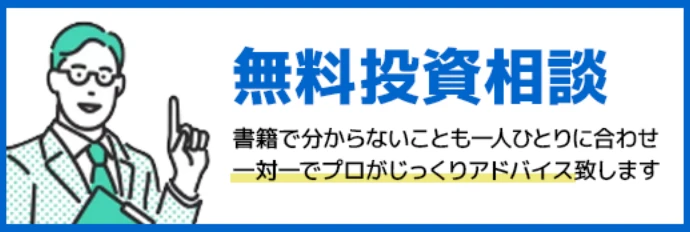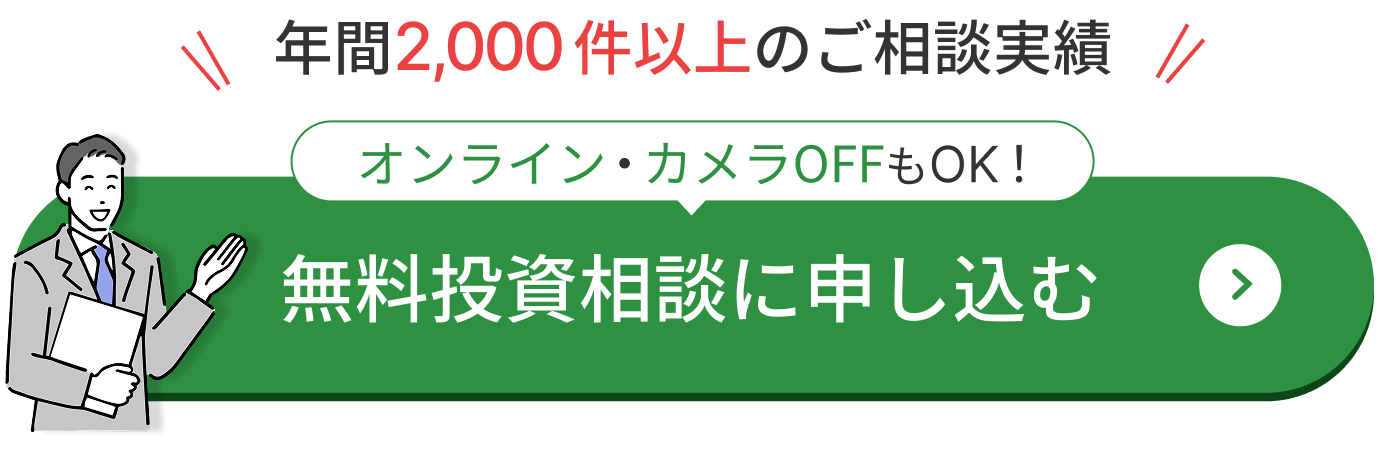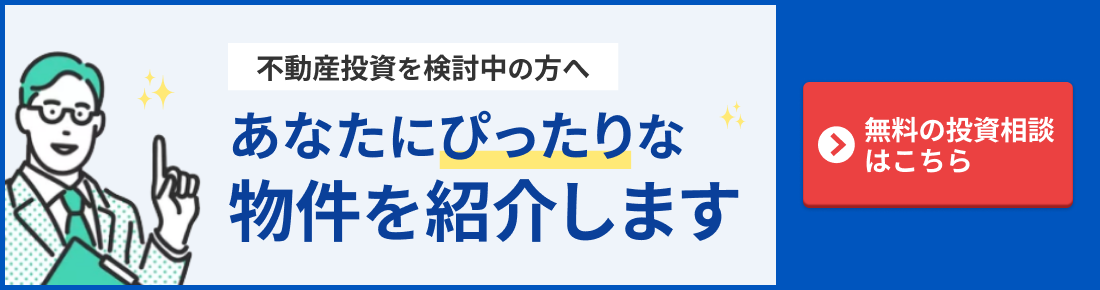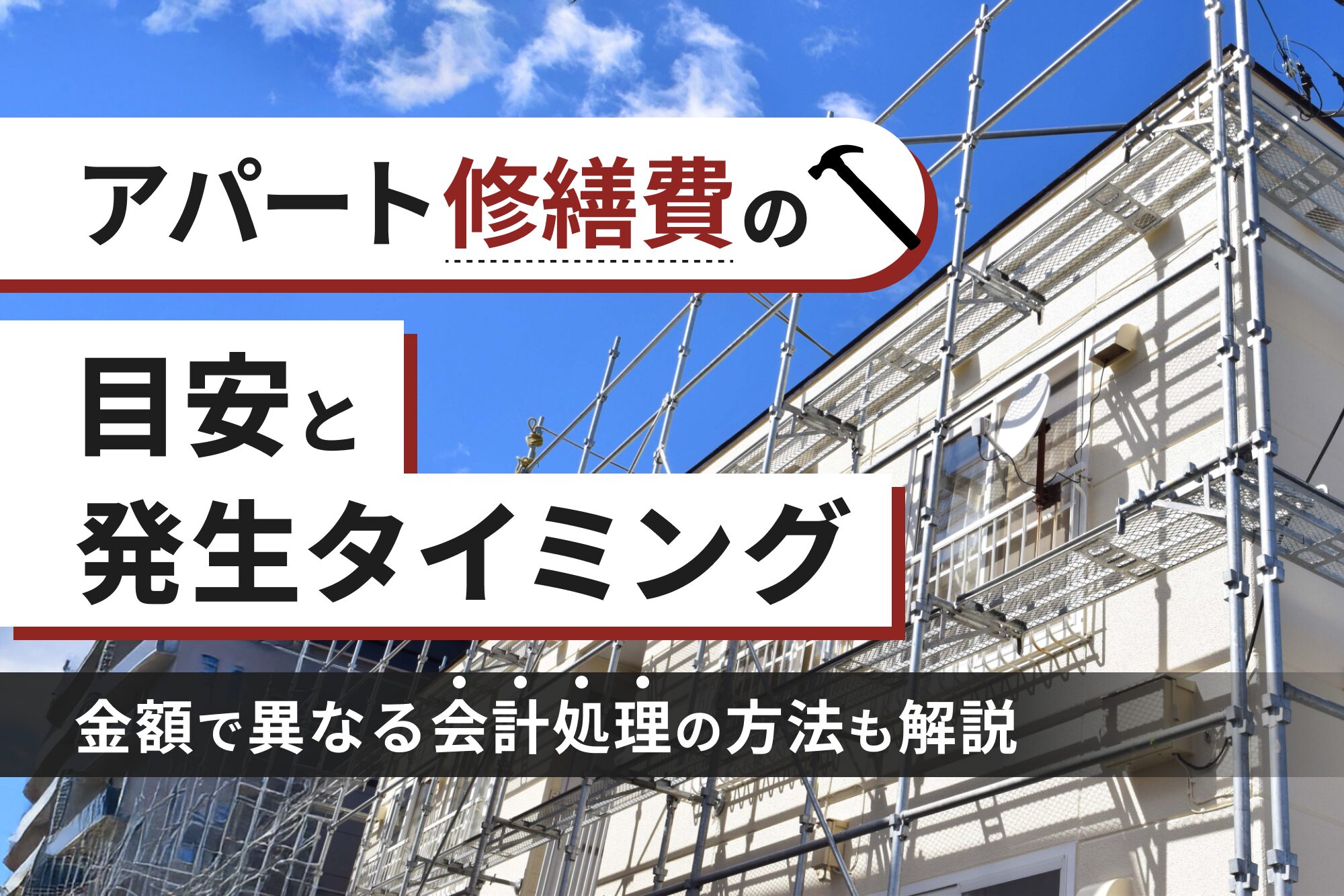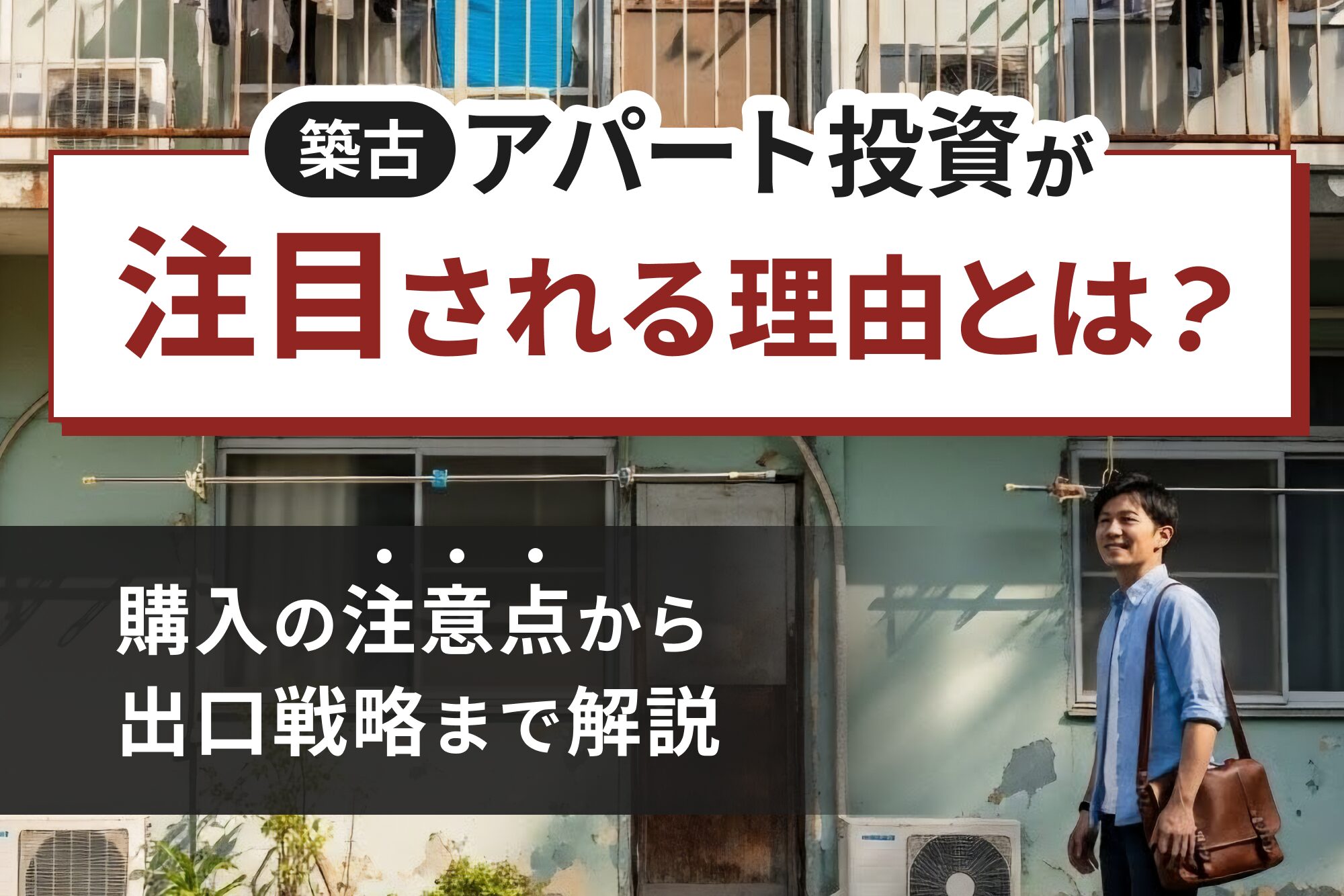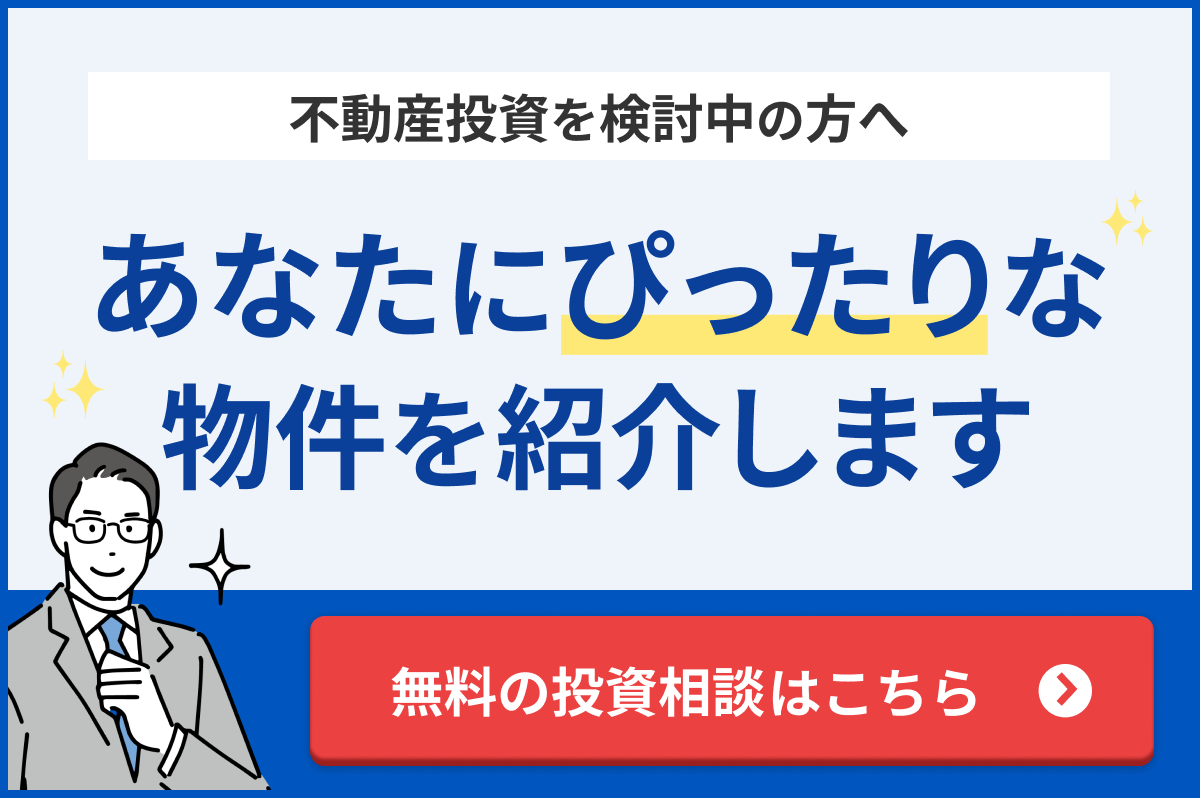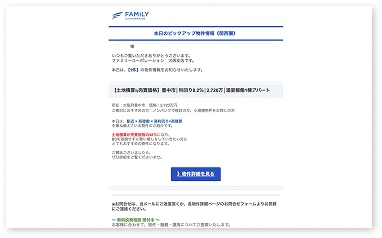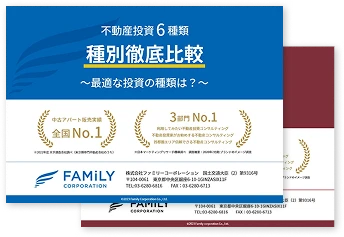アパート経営の初期費用はどのくらいかかる?必ず押さえたいポイントを解説

目次
アパート経営を始める際には相当額の初期費用が必要です。しかし、「具体的にどの程度の資金を用意すべきか」「初期費用をどのように算出すればよいのか」といった点が分からず、戸惑う方が多いかもしれません。
そこで本記事では、アパート経営にかかる初期費用の目安やシミュレーションの方法を解説します。初期費用をおさえるコツや運用時に発生する費用も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
アパート経営では、物件価格だけでなく諸費用や運用コストまで含めて資金計画を立てることが重要です。しかし、実際には初期費用の算出方法が分からず、不安のまま検討が進まない方が多いのも事実です。
ファミリーアセットコンサルティングでは、あなたの年収や資金状況に合わせて、初期費用の目安から融資条件、無理のない運用計画まで、最適なシミュレーションを無料でご提案しています。
相談者限定で高利回りの非公開物件もご紹介できるため、より現実的な判断がしやすくなります。アパート経営を安全に始めたいと考えている方は、この機会にぜひ無料投資相談をご利用ください。
アパート経営にかかる初期費用

アパート経営には、「新築や中古のアパートを購入する方法」と「所有している土地、あるいは購入予定の土地にアパートを新築する方法」の2パターンがあります。
建築予定の物件や中古の物件を購入する場合は、売りに出ている情報から物件価格が分かります。
ここでは、所有している土地や購入予定の土地にアパートを新築する場合の建築費用について解説します。
本体工事費
本体工事とは、仮設工事、土木工事、基礎工事、外装・内装工事など、本体を完成させるまでの工事費用を指します。建設費は全体の7〜8割を占め、高額になる傾向があります。
立地条件や建物のグレード、建築資材などにより費用は変動しますが、初期費用をおさえようと安価な資材を使い過ぎるのは避けたほうがよいでしょう。建物が傷みやすくなり、修繕費や維持費がかさむ恐れがあります。
別途工事費
別途工事費とは、設備や地盤に関する工事費用のことです。工事内容は不動産の用途により異なりますが、主な工事は以下の通りです。
- 地盤改良工事
- 外壁工事
- 整地工事
- ガス管や水道管の設置工事
- 電気や空調設備の取り付け工事
別途工事費は、一般的に本体工事費の20%程度と見積もられます。上下水道・ガス管の長さが長い場合や、地盤改良に手間がかかる場合は費用が増える傾向にあります。また、古い建物を解体して新築する場合は、解体費用も別途必要です。
初期費用を適切に見積もることは、事業計画を立てる上で重要です。専門家に相談するなどして、的確な情報収集に努めましょう。
アパートの建築費用の計算方法
アパートの建築費用の総額は、以下のように坪単価と延べ床面積で計算できます。
建築費用=坪単価 × 延べ床面積
例えば、坪単価60万円、延べ床面積60坪のアパートの建築費用は3,600万円なります。
建築費用は新築の物件でアパート経営を始める際の最大の初期費用であるため、必ずおさえておきましょう。
アパートの建築の坪単価の相場
アパートの建築費用は規模や工法、建築する場所の法令によって異なりますが、坪単価の相場はおおむね以下の通りです。
| 木造アパート(2~3階建て) | 1坪当たり49万円~115万円程度 |
| 鉄骨造アパート(2~4階建て) | 1坪当たり56万円~115万円程度 |
(参考: 『政府統計の総合窓口(e-Stat):建築着工統計調査 住宅着工統計 2023年次 第34表』)
木造アパートは鉄骨造アパートと比較すると低コストで建築できます。一方、法定耐用年数は木造アパート22年、鉄骨造アパート(骨格材肉厚4mm以上)34年であるため、鉄骨造アパートのほうが長期にわたって資産価値を維持しやすいでしょう。
また、建設するアパートの階数によっても単価が異なり、階数が上がると建築費も上がります。初期費用を安くおさえたいときは木造の低層アパート、効率的な集客や長期経営を目指すなら鉄骨造の高層アパートが望ましいでしょう。
アパート経営の初期費用:諸費用

アパート経営において、物件の頭金以外にも税金、手数料、保険料などさまざまな諸費用が必要となります。諸費用は、新築で購入価格の4%〜7%程度、中古で7%〜10%程度が目安です。例えば、物件価格が5,000万円の場合、諸費用は350万円(5,000万円×7%)程度になると推定できます。ここでは、主な諸費用の概要や注意点、税率などについて解説します。
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登記費用
- 融資事務手数料
- 損害保険料
- 仲介手数料
- 司法書士への報酬
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を取得する際に課される税金です。計算式と税率は以下の通りです。
計算式: 固定資産税評価額 × 税率(3%)= 税額
固定資産税評価額とは毎年1月1日時点での土地や建物の価格を指し、国が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が評価・決定します。土地や建物の購入価格・建築費とは異なるため注意しましょう。
固定資産税評価額の目安は土地の場合は時価の70%程度、建物の場合は50〜60%です。令和6年3月31日までに宅地など(宅地および宅地評価された土地)を取得した場合は、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。また、現在は「新築住宅・住宅用地特例」という制度も設けられており、一定の要件を満たせば適用が可能です。
例えば、土地評価額4,000万円、建物評価額2,000万円のアパートを購入した場合の不動産取得税は以下の通りです。
≪土地≫
土地評価額4,000万円 × 1/2 × 税率3% = ①土地の不動産取得税60万円
≪建物≫
建物評価額2,000万円 × 3% = ②建物の不動産取得税60万円
≪土地・建物≫
① + ② = 不動産取得税120万円
合計で120万円の不動産取得税を納める計算となります。なお、不動産取得税には軽減措置があり、要件を満たす場合は上記計算よりも少ない額になります。
幅広いケースで受けられるため、より詳細に知りたい方は以下のページをご覧いただくか、業者、もしくは税事務所等への問い合わせてみましょう。
(参考: 『東京都主税局』)
不動産取得税は、最寄りの都道府県税事務所に申告後に届く納税通知書をもとに支払いを行います。納税期限は地方自治体によって異なるため、書類をよく確認し記載の期日までに納税しましょう。
印紙税
印紙税は経済取引の際に発行される領収書や契約書などの課税文書に対して課される税金であり、不動産投資では売買契約書やローンを組む際の金銭消費貸借契約書の作成時に納税が必要です。
印紙税の税額は契約金額によって変わり、以下の通りです。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減税額 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
印紙税は軽減措置が講じられており、2027年3月31日までは上記の軽減税額が適用されます。
なお、軽減措置の対象は不動産売買契約書に記載された契約金額が10万円を超える場合に限られますが、アパート経営に取り組む際の物件の価格帯を考えると非常に稀なケースであるため、軽減税額が適用されると考えてよいでしょう。
登記費用
アパート経営をする際は、不動産の権利関係を明らかにするための不動産登記に関連する費用が発生します。
土地の売買や中古物件の購入の際は「所有権移転登記」、新築物件の購入の際は「建物表題登記」や「所有権保存登記」、融資を受ける際は「抵当権設定登記」を行い、その際に必要となるのが登録免許税です。
建物表題登記は、登録免許税はかかりませんが土地家屋調査士に依頼する場合は、報酬を払う必要があります。費用の相場は、9~12万円程となります。
所有権移転登記と所有権保存登記の登録免許税は「固定資産税評価額×税率」によって決まり、抵当権設定登記は融資を受ける額によって変わります。
【所有権移転登記】
| 売買 | 登録免許税=固定資産税評価額×2% |
| 相続・法人合併・共有分割 | 登録免許税=固定資産税評価額×0.4% |
| 贈与・遺贈・競売 | 登録免許税=固定資産税評価額×2% |
登録免許税には軽減措置が設けられており、土地の売買に関しては1.5%に軽減されています。
【所有権保存登記】
固定資産税評価額×0.4%
【抵当権設定登記】
債権金額(融資を受けた金額)×0.4%
なお、登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、司法書士手数料は依頼する司法書士によって異なります。所有権保存登記と抵当権設定登記を合わせて6万円〜7万円程度が相場です。
また、司法書士に支払う報酬は不動産所得の経費に算入できます。領収書を保管し、いつ・何を依頼したのか、忘れないように記録しておきましょう。
融資事務手数料
融資事務手数料は、不動産投資ローンを組む際に金融機関に支払う事務手数料です。手数料は金融機関により異なり、定額型と定率型の2パターンがあります。
- 定額型:3万円〜10万円程度
- 定率型:借入金額に対して一定の割合(通常1〜3%+税)を支払う
定額型か定率型のどちらが割安になるかは、ケースによって異なります。
損害保険料
火災保険や地震保険に加入する場合、保険料も初期費用に含まれます。保険への加入は義務ではありませんが、リスク対策として重要です。また、ローンを組む際に火災保険の加入が義務付けられることもあります。
火災保険は、火災だけでなく以下のような災害も補償対象となります。
- 破裂、爆発
- 落雷
- 風災、雹災(ひょうさい:大粒の雹(ひょう)による損害)、雪災
- 水災
- 水濡れ
- 外部からの飛来、落下、衝突
- 騒擾(そうじょう:騒いで秩序を乱すこと)や集団行為などに伴う暴力行為
- 盗難
ただし、地震による災害は対象外のため、地震保険は火災保険に付帯して加入し、地震に伴う火災や建物損壊などに備えることになります。
保険料は保険期間や物件の構造により大きく異なります。
仲介手数料
不動産会社に仲介を依頼してアパートを取得した場合は、売買契約成立時に仲介手数料の支払いが必要です。仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法によって以下のように定められています。
| 取引価格(税抜) | 計算式 |
| 200万円以下 | 物件価格×5%+消費税 |
| 200万円〜400万円以下 | 物件価格×4%+消費税 |
| 400万円以上 | 物件価格×3%+消費税 |
ただし、上記の計算式は複雑なため、400万円を超える物件については、以下の速算式で計算するのが一般的です。
【速算式】
仲介手数料の上限=物件価格×3%+6万円+消費税
例えば、5,000万円(税抜)の不動産を購入した場合、速算式に当てはめると171万6,000円になります。
5,000万円(税抜)×3%+6万円+(消費税10%)=171万6,000円
なお、不動産会社が売主の場合(一般の売主から直接アパートを購入する場合も含む)は、仲介手数料は発生しません。
アパート経営の初期費用をシミュレーション

アパート経営の初期費用は、おおむね物件購入価格の1割程度が目安とされています。所有している土地を活用するために新築アパートを建てる場合と、中古アパートを購入する場合をシミュレーションしてみましょう。
【新築アパートを建てる前提条件】
- 建物:木造アパート2階建て
- 借入:2,500万円
- 坪単価:60万円
- 延べ床面積:60坪
【中古アパートを購入する前提条件】
- 借入:3,600万円
- 土地の固定資産税評価額:1,300万円
- 建物の固定資産税評価額:1,800万円
| 種類 | 新築アパート | 中古アパート |
| 建築費(本体工事費) | 3,600万円(60万円×60坪) | - |
| 建築費(別途工事費) | 720万円(3,600万円×20%) | - |
| 物件購入価格(土地・建物) | - | 4,500万円 |
| 不動産取得税 | 54万円(3,600万円×1/2×3%) | 72万円(1,300万円×1/2×3%=18万円、1,800万円×3%=54万円) |
| 印紙税 | 1万円 | |
| 所有権保存登記 | 7万2,000円((3,600万円×1/2×0.4%=7万2,000円、) | - |
| 所有権移転登記 | - | 55万5,000円(1,300万円×1.5%=19万5,000円、1,800万円×2%=36万円) |
| 抵当権設定登記 | 10万円(2,500万円×0.4%) | 14万4,000円(3,600万円×0.4%) |
| 融資事務手数料 | 約6万円(※定額制) | |
| 損害保険(火災・地震保険) | 約40万円(5年一括払) |
|
| 仲介手数料 | - | 66万円(1,800万円×3%+6万円+消費税10%) |
| 司法書士への報酬 | 約7万円 | |
| 合計 | 4,445万2,000円 | 4,747万4,000円 |
自身でシミュレーションするのが難しければ、不動産会社に実際の物件情報に基づく見積書の提示を依頼するとよいでしょう。
ローンと頭金(自己資金)の目安

頭金とは、物件価格からローンの借入額を引いた金額であり、物件購入時に現金で支払うお金を指します。
不動産投資のローンの審査は本人の属性や返済能力だけでなく、購入する物件の収益性や条件についても対象になります。
フルローンは融資審査の難易度が高いため、一般的には物件価格の10〜30%程度の頭金が必要になると考えておきましょう。一方で、返済比率(ローン残高/物件価格)の目安は50%以下が一般的です。
頭金を多くすると融資額をおさえられるため、毎月の返済額が少なくなります。一方で、頭金を少なくする場合は手元に資金を残しておけるため、運用中の修繕費用等に充てられるといったメリットがあります。
ただし、「頭金を少なくして長期返済したい」場合でも、必ずしも希望通りの融資が受けられるとは限りません。経営リスクをおさえるためにも、頭金は少なくとも30%程度用意することが賢明です。
自分の組める融資条件によって「どのくらいの頭金が必要なのか」「どのような物件を購入できるか」が変わってきます。まずは、どのような融資条件で取り組めるかを不動産会社に確認しましょう。
アパート経営の初期費用をおさえるポイント

初期費用をおさえることで手元に資金が残るため、修繕等の突発的な対応が必要になった際に対応しやすなるでしょう。初期費用をおさえるためのポイントは以下の通りです。
- 不動産会社が売主の物件を購入する
- 金融機関とのコネクションが強い不動産会社を探す
- 銀行からの評価が高い物件を購入する
不動産会社が売主の物件を購入する
不動産会社が売主の物件を購入すると買主と売主の直接の契約となり、不動産会社による仲介がないため仲介手数料を支払う必要がなくなります。仲介手数料は初期費用の多くの割合を占める部分であるため、おさえられれば数十万円〜数百万円もの費用の節約につながります。
不動産会社が売主となっている物件は不動産ポータルサイトでは「売主」や「代理」という文言が記載されているため、購入する際の参考にしてみてください。
金融機関とのコネクションが強い不動産会社を探す
付き合いのある金融機関や検討中の金融機関がない場合は、取引金融機関が多い不動産会社を探してみましょう。
金融機関とのコネクションが強い不動産会社を通して購入すると、通常よりも金利が低い独自のローンを利用できるケースがあります。不動産投資は融資の条件や金額によって収益性が異なるため、物件だけでなく融資についても情報を集めましょう。
例えば、返済期間30年で2,000万円のローンを組んだとしましょう。金利1.5%の場合は総返済額が2,485万円ですが、金利2%になると2,661万円となり、200万円近い差が出ます。不動産の規模にもよりますが、賃料収入で200万円もの金額を回収するには多くの時間がかかるため、効率良く投資するためにも融資を上手に活用しましょう。
ファミリーアセットコンサルティングは、40行以上の金融機関との取引実績がございます。不動産投資をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
銀行からの評価が高い物件を購入する
不動産投資を行う際に金融機関からの評価が高い物件を選べば融資金額が伸びる可能性があるため、頭金をおさえての購入が可能です。不動産の評価は積算価格や収益価格によって求められます。
- 積算価格:今現在同じ土地、同じ建物(経年劣化を含む)を建てた場合にかかる価格
積算価格=土地の価格+建物の価格
土地の価格=路線価×土地面積
建物の価格=再調達価格×延床面積×(法定耐用年数-築年数)÷法定耐用年数
- 収益価格:不動産から得られる収益やかかる費用、適正利回りをもとに算出する価格
収益価格=年間運用純利益÷実質利回り
※年間運用純利益は家賃収入から年間経費を差し引いた金額
なお、評価基準は金融機関によって異なるため、融資状況に詳しい不動産会社に相談するのがおすすめです。
金融機関からの評価が高い物件は資産価値が高い証でもあるため、投資の際の安心材料にもなります例えば、大通りに面している土地や築年数の浅い物件、法定耐用年数の長い鉄筋コンクリートなどで作られている物件は資産価値が高い傾向があります。
初期費用をおさえつつ安定的なアパート経営を行うには
初期費用をおさえつつ、アパート経営を行うには新築物件よりも中古物件のほうがおすすめです。中古物件は同規模の新築物件よりも取得費が割安であるため、初期費用をおさえられます。また、入居率などのデータもあり、賃貸需要があるのかを事前に確認できる点も魅力です。賃貸需要が高い立地の中古物件を選べれば、安定した家賃収入につながるでしょう。
一方、新築物件には初回の入居者を集めやすいという利点がありますが、資産価値の低下が比較的早期に生じるとされています。また、取得費が割高であるにも関わらず、利回りが低くなりやすいという懸念点もあります。
アパート経営に適した中古物件を選ぶ場合は、東京圏や関西圏の中古物件が狙い目です。東京圏や関西圏の人口は増加傾向にあり、地方の物件と比べると高い賃貸需要と低い空室率が期待でき、アパート経営をするための好条件がそろっています。
アパート経営にかかる運営費用も試算しておこう

アパート経営の運用をする際は以下の費用がかかります。
- ローン返済
- 管理委託手数料
- 修繕費
- 原状回復費
- 広告費
- 固定資産税や都市計画税
- 所得税や住民税
上記はアパート経営をする際の経費に該当し、家賃収入から差し引いた金額が利益になります。
ローン返済
不動産投資ローンを利用してアパートを購入した場合の返済金額は、借入金額・返済期間・返済方法・金利によって変わります。
ローンの返済方法には、「元利均等返済」と「元金均等返済」の2パターンがあります。
| 元利均等返済 | ・返済額(元金+利息)が一定のため返済計画が立てやすい ・ただし、総返済額が元金均等返済より多くなる |
| 元金均等返済 | ・返済額が徐々に減少する ・総返済額をおさえられるが、当初の返済額が大きく、ローン審査で希望額が借りられない可能性がある |
また、金利にも種類があります。
| 固定金利 | 金利が一定(固定)で返済計画を立てやすい |
| 固定金利選択型 | 一定期間は固定、期間経過後は金利が変動する |
| 変動金利 | 定期的に金利が変動し、返済額が増減する |
変動金利は固定金利よりも低利率に設定されている傾向がありますが、世界情勢次第で金利が上昇するリスクがあります。金利変動リスクを回避したい場合は固定金利を選ぶとよいでしょう。また、金融機関によっては選択できない場合もあるので注意が必要です。
管理委託手数料
管理委託手数料は、アパートの運営にかかわる管理を不動産管理会社に委託する際にかかる費用です。手数料の相場は家賃収入の5〜10%程度とされています。管理会社に委託できる主な業務は次の通りです。
- 入居者募集
- 賃貸借契約締結/更新
- 家賃回収/家賃滞納者への督促
- 解約手続き/退去時の立会い
- クレーム処理
- 清掃
- 法定点検
- 室内クリーニング
- リフォーム
管理委託手数料は、オーナー自身が管理業務を行えば発生しません。しかし、煩雑かつ手間がかかるため、管理会社に委託したい方が多いのではないでしょうか。高額な費用をかけずにオーナーの負担を大きく軽減できるため、費用対効果は高いといえます。
修繕費
修繕費は建物や設備の不具合が発生した際にかかる費用です。一戸建てや1棟アパート・マンションなどの場合は室内だけでなく、共用部に対しての費用も必要になります。
外壁塗装などは修繕が必要な時期をある程度見積もりやすいですが、建物内部の設備や給排水管などはいつ故障するか分かりません。所有している戸数が多ければ多いほど突発的な不具合が生じるケースが多くなるため、日頃から修繕費は積み立てておきましょう。
国土交通省のデータによると、必要な修繕費の目安は以下の通りです。
| 鉄筋コンクリート造10戸(1K) | 木造10戸(1K) | |
| 5〜10年目 | 約7万円/戸 | 約7万円/戸 |
| 11〜15年目 | 約46万円/戸 | 約52万円/戸 |
| 16〜20年目 | 約18万円/戸 | 約18万円/戸 |
| 21〜25年目 | 約90万円/戸 | 約80万円/戸 |
| 26〜30年目 | 約18万円/戸 | 約18万円/戸 |
| 合計 | 約177万円/戸 | 約174万円/戸 |
(参考: 『国土交通省 民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック』)
築年数が経過した物件であるほど修繕費がかさみやすいため、中古物件を購入する際は注意しましょう。
原状回復費
原状回復費は入居者が退去する際に室内を借りたときの状態に戻すための費用です。通常、原状回復費は入居者が支払う部分とオーナーが支払う部分に分かれています。例えば、室内に故意で傷つけられた箇所があったり、タバコのヤニで部屋全体が黄ばんでしまっていたりする場合は入居者の費用負担で原状回復をします。
一方で、壁紙や床の日焼けなど経年劣化によるものはオーナーが負担しなければなりません。入居者が負担する場合は、入居時に預かった敷金から修繕し、余った金額は退去時に返還します。原状回復費は室内の広さや状況などによって費用が大きく異なるため、一概に目安は提示できません。
広告費
入居者募集の際に不動産会社に広告運用を依頼した場合は広告費が発生します。広告費は入居者募集をするためにオーナーが不動産会社に支払う費用であり、特別な広告を依頼した場合は別途費用がかかる場合があります。
物件の家賃が周辺の相場より高すぎたり、初期費用が多すぎたりする場合は広告費をかけても、入居者が見つかるまでに時間がかかるケースもあるため、家賃設定が適正かを考え判断しましょう。
固定資産税・都市計画税
不動産取引の公平性を保つため、不動産の売買においては固定資産税・都市計画税の精算が行われます。通常、1月1日時点での所有者が年間分の税金の納税義務者となりますが、年度の途中で売買があった場合でも元の所有者が全額を負担します。しかし、この方式では不公平が生じることから、実際の取引では引渡し日を基準に日割り計算して精算を行うのが慣行となっています。
固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対して課される税金です。一方、都市計画税は原則として市街化区域内の土地および家屋に課税されますが、物件の立地条件によっては非課税となる場合もあります。
【税額の計算式】
- 固定資産税:固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%
- 都市計画税:固定資産税評価額(課税標準額)×0.3%
※自治体によって税率が異なる場合もあります
納付方法は毎年1年間の納付額を4分割するか、一括で全額納付するか選択可能です。固定資産税と都市計画税は毎年かかるため、あらかじめ発生する費用をおさえておきましょう。
所得税や住民税
所得税と住民税は1年間の家賃収入から経費を差し引いた課税所得に対して課される税金です。所得税の税率は5〜45%であり、累進課税であるため課税所得が増えるほど税率は高くなります。住民税の税率は市民税が6%、都道府県民税が4%です。
| 税金の種類 | 特徴・計算式 |
| 所得税 | ・不動産で得た収入(不動産所得)は給与所得と合算される ・合算した金額から必要経費や控除を差し引いた「課税所得」をもとに税金が計算される ・帳簿上での不動産投資赤字と、給与所得との合算(損益通算)で所得税の節税効果がある ・計算式:所得税 = 課税所得額 × 税率 - 税額控除 |
| 住民税 | ・都道府県民税と市区町村税が合わさったもの ・所得税と同様に所得に対して課されるため、所得税が下がると住民税も下がる ・前年の所得をもとに計算するため、不動産投資の節税効果が出るのは翌年から ・計算式:住民税 = 課税所得額 × 税率 - 税額控除 + 均等割 |
不動産投資は税金が大きなランニングコストとなります。減価償却費など経費計上できる費用をもれなく網羅して課税所得をおさえ、節税につなげましょう。
まとめ

アパート経営をする際はアパートの建築費や税金、仲介手数料などさまざまな初期費用がかかります。「不動産会社が売主の物件を購入する」「金融機関とのコネクションが強い不動産会社を探す」などの方法を活用して、費用をおさえましょう。
また、物件選びの際に中古物件を選ぶのも初期費用をおさえるポイントです。中古物件は同規模の新築物件より取得費が割安な上に、安定した利回りも期待できます。
「アパート経営における初期費用が知りたい方」「借入の限度額が知りたい方」「融資を前提にアパート経営を考えている方」は、ぜひファミリーアセットコンサルティングにご相談ください。融資の最新情報や初期費用を低くおさえるコツなどを無料で解説いたします。
監修者プロフィール